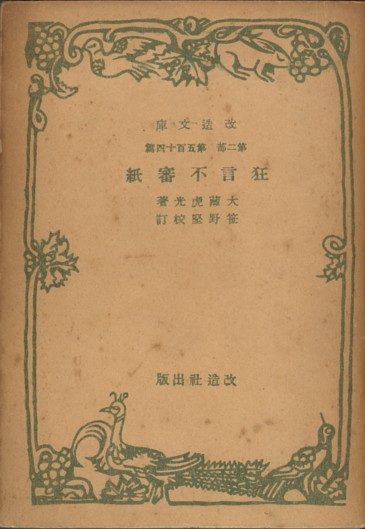
| らんだむ書籍館 |
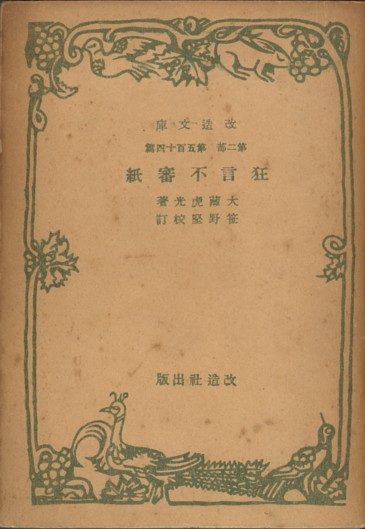
|
|
表紙 |
夫れ狂言は、神代のむかし天のうずめの命のみ心より始りしとは、旧事記の巻にも云ふ。 式正の事は、聖徳太子の古へより今なを家に秘して伝わりぬ。 宇治拾遺に、堀川院の御時、内侍所の御神楽の夜、職事家綱に「珍らしからぬことつかふまつれ」と仰せ事ありしに、行綱謀りて細脛を出して猿楽せしと源氏物語などにも見へ、今様狂言は比叡の山北畠にありし玄恵法印のつくれる数多し。 抑も狂言とは、狂ふ言と書きて権は実とし実は権として権実も定かならず、有は無の初めなれば有無もさだかならず。 是れ、狂言綺語も讃仏乗の因縁とかや。 唯、倚(かたよった)たるも直なるも思ふまにまに言の葉に述べ、その様をなして狂言の狂言たるはいと愛度(めでたき)ものなれば、かしこくもおほやけの御式にも其の業をなすはおほけなき事、云ふもさらなり。 只古雅を守る事をむねとし、世俗のこと葉をまぢへず、不審の数の多きは、かんゐんのおほいきみの詠み給へる「むかしより思ふこゝろはありそ海の浜の真砂はかずもしられず」と、歌の心はいかなるか、我が此の道も不審に思ふ心の数も知れねば、狂言不審紙と題してたらちねの教へしことなど、そのひとつ二つをしるしおきぬ。この意図に沿って、167番の狂言について難解な語や重要な語の解釈が試みられている。
文政六のとし 癸未初秋 虎光
| 本書の構成とその混乱 |
|
目 次
例 言 解 説 狂言不審紙 春 狂言不審紙 夏 狂言不審紙 秋 狂言不審紙 冬 曲目索引 |
| 博引旁証 |
実を教へ実を習ふこそ専要なれ。 つれつれ草九十二段に云ふ、弓射る事を習ふに諸矢手挟みて的に向ふ、師の云はく、初心の人ふたつの矢を持つ事なかれ、後の矢を頼みて初めの矢に等閑の心あり。 毎度ただ得失なく此の一箭に定むべしと思へと言ふ。 わつかに二の矢、師の前にて一つを愚かせんと思はんや、懈怠の心自知すと云へども師是をしる。 此のいましめ万事に渡るべし。 …「懈怠の心自知すと云へども」の部分の原文は、「懈怠の心みづからしらずといへども」である。 虎光は、自分の思い込みによって記しているのかもしれない。 「自知すと云へども」の方が厳しさがある。
俳優考に云ふ(家宣将軍御寵愛の御儒者・新井筑後守白石先生の書)、室町殿の比(頃)ほひ、狂言といひしものは、其の様は古へより有りし狂言をなせしにはあらず、其の時に臨みて珍らかにおかしき事を作り出せしなり。 髪ゆふ事を嫌ひし狂言は、その頃鎌倉殿の御事にて、人の誉むる事を悦びて、物人々にくるゝ狂言は、其の比の公方の御事なり。 詞をさかしまにしていふことは、其の比東国の俗にて有りしを、そのならはしの都に移りて、よき人ももて興じ給ひしなり。 其の比には斯く其の君を正し参らすべき事を、狂言に取りなして諌め参らせしなり。 末の世には有り難き事なりと、それがしが師にて候ひし者は申しき。「麻生」では、続いて、詞の中のいろいろな語について、考証が行なわれている。
按ずるに、髪結ふを嫌ひしとは、矢張り此の麻生の狂言の事なるべし。
膠鯉煎(キヤウリセン)。 狂言造り物にては、檜木口にて金壹寸五分、丸く、長さ壹尺五寸なり。ここにも「徒然草」が引かれている。 文中の「鬢そゝけず」は、鬢が乱れない、という意味。
鯉の鱗を煎じて、水飴などのよふに木に巻きて用ゐると云ふ。
徒然草文段抄四百十八段に云ふ、鯉のあつ物食ゐたる日は、鬢そゝけずとなん。 膠にも作る物なれば、ねばりたる物にこそ。 此の段には、鯉の功能を云ふ。 次に故実を書く。 此の国の昔の風俗をかけり。 鯉のあつ物喰ゐたる日は、鬢そゝけず。 此の事、本草には見へず。 昔は日本の医書余多有りければ、其の中などに記せるか。 寿抄再野に、魚を膠に作る、鰾(ニベ)と言ふ。 瑣酔録に、鯉魚膠を墨に摺りて身にさせば、青黒にして愛すべしとあり。 今は油にて髪を結ふによりて、何か異といへども、能く昔を尋ぬべし。
「九重の都」と称ふるは、周礼匠人職に出たり。 「匠人の国を営むこと、方九里」は、周の天子の代の太子の都の広さなり。 四方に三門づつ有りて合せて十二門なり、十二門は通じて十二支とす。 旁らに三門有り。 「国中、九経九緯、云々」。 国中と言ふは皇城にして宮城の事にあらず、経緯とは道條(スジ)にして、南北を経(タテ)とし、東西を緯(ヨコ)とす。 一門毎に三條の道有りて、東西各九條有り、是を九重と言ふ。 都とは華(ミヤビヤカ)の訓なり、花の都とも名付く。引用した「周礼」の文について非常に丁寧で適確な解釈がなされているのは、おそらく専門家(漢学者)の説明を聞き、それを利用したのであろう。
包丁聞書に云ふ改敷、四條家包丁書に云ふ掻敷、皆鋪、飼敷と見へたり。 同書にカイシキの事は、檜葉、南天燭とあり。ここで引かれている荻生徂徠の「なるべし」も、たびたび参照されている書籍である。
なるべしに云ふ(徂徠先生の随筆なり)、なんてんは南天燭なり。 田舎人はなでんと云ひ、又らんてんと言ふ人あり。 八種画譜に蘭天竹と云へり。 唐も和も、らとなとはかよふ成るべし。
ある人云ふ、南天は元来南天竺国より渡りたる物也と云へり。 さすれば、なんてんじくといへるが正しきか。 何によらず、異国より渡りたる物を、其の国の名を物の名に呼ぶことあり。
大和物語に云ふ、昔、津の国に住む女有りけり。夫れをよばふ男二人なん有りける。 ひとりは其の国に住む男、姓はむはらになん有りける。 いま独りはいづみの国の人になん有りける。 姓はちぬとなんいひける。「鎧」のところには、大筒すなわち鉄砲の伝来についての、要領のよい説明がある。
万葉集には、莵原牡子と書きて、うなひおとことよめり。 又、莵会処女ともあるを、仙覚抄の説に莵会は所の名といへり。 されど、いせ物語にも、うはらのこほりあしやの里とあれば、うはらうない同じ事にや。 万葉集に、血沼壮士その夜夢みてなん侍る。 歌には、
塚のうへの木の枝なひけりきくかこと
陳努壮士にもよるへけらし
葦屋処女の墓、能には求塚、千奴笹田の万次郎うなひ、おと女を恋して言ひよりけるに、何れへ返事もなし難く、いく田川に浮く鳥を射て当りし方へ返事すべしと定め、鳥を射けるに同じ矢つぼに当りければ、女はせん方なく生田川へ身を投げ、空しく成りければ、二人の万次郎男も空しく成りけるとなん。
按ずるに、此の物語りを秀句しての作意成るべし。
或る人言ふ、大筒とは鉄炮之事。 …「文相撲」のところには、相撲四十八手についての説明がある。
弘安三、蒙古国より日本を責し時、持ち来る。 其の時、日蓮上人甲斐国身延山に有りて、旛曼荼羅を書く。 是を先に押し立て、宇都宮高綱先陣にて向ふ。 妙法の弘力に依て蒙古勢悉く退治す。 其の時取り落したると云ふ。 然れども其の術をしらず。 天文のころより始りしと云ふ。
和泉図会に云ふ、鉄鉋は、(又、鳥銃とも言ふ。)天文年中、南蛮の大船筑紫に来る。 種が時嶋堯(タカ)と云ふ者、蛮賈長牟良叔舎喜利志侘孟太の両人に遇ひて、鉄炮の術を習ふ。 其の後、堺の津橘屋又三郎と云ふ者、交易の為、種が嶋に滞留の時、鉄炮製受す。 帰国の後、多く作ると云ふ。 又一説には、永正年中、異国より初めて和泉国堺に渡す。 其の比(頃)相州小田原に玉龍坊と言ふ山伏有り、鉄炮を堺より求め、北條氏綱に献ず。 氏綱の長男氏康、鍛冶国康を呼びて多く作ると云ふ。
按ずるに、此の狂言の作より鉄炮の始りしは後と考ふ。 惣じて狂言に鉄炮と云ふ事は、後の附弁ならぬか。
相撲四十八手。「楽阿弥」のところでは、「何をか不審し給ふらんあの宇治の、ろうあんじの尺八のぢよにも、…」という詞について、次の解説がある。
よつがひ まがいつき出し きぬかづき 飛ちがひ たし かものいれくび 大わたし しゆもくぞり(撞木反) ひさこまはし やくら 河津繋 ためだし うとむそじ こまた さか手なげ かいなひねり(腕捻) うちむそじ うわ手すかし したてやくら やがら のぼりがけ こしくじき つきやくら たくり(手繰) しき(鴫)の羽かへし そくびなげ みところつめ もち出し なけ そとがけ こつまとり しきこまた はりまなげ ひむまわし くじきたをし てうながけ とあし けかへし つゝきけかへし ぎやく投 すくひ投 うちかけ かたすかし むかうづき かけ(繋)なげ おひ(笈)なげ あおりかけ(泡障掛) そくびおとし
古ハ相撲ヲ以テ武芸ノ其ノ一トス。 故ニ禁中ニ於テ毎年相撲ノ節会アリ。 武士各々相撲ヲ練習ス。 歩戦組打ノ為ナリ。 相撲四十八手、葉室大納言時長卿ノ源平盛衰記衣笠合戦の條ニ、武蔵国綴喜党ノ大将ニ太郎五郎トテ、兄弟二人相撲ノ上手、四十八手ニクラカラズ見ヘタリ。 又虎関和尚ノ異制訓ニ、相撲四十八手之取手有リ。 所謂、入相撲懸相撲[足+昜]相撲内絡外絡等ナリト見エタリ。 手ノ名、古今変改アル歟、四十八手ハ古ヨリ有リシ事ナリ。
宇治黄檗山萬福寺の門前南ニ町に、普化の墓あり。 伝に云ふ、中頃虚無僧の祖・普化良庵と云ふ者の塚有り。 古、此の地は竹林にして、都鄙の虚無僧等、竹を争ひ截りて尺八に作る故に、今荒廃す。 原(もと)の普化禅師は異国の人なり。 此の良庵と云ふ者、其の宗風を慕ふ。 専ら尺八を愛し四方に遊ぶ、世の人、是を呼びて和朝の普化と称すと云ふ。このように、虎光の考証は、多方面にわたり、かなり細かな事項にまで及んでいる。
両頭於疑説談而
尺八寸内通古今
吹起無常心一曲
三千里外絶値因
此の四句は、京都池田町妙安寺より出る本則奥書なり。
按ずるに、「尺八のぢよにも」と云ふは、掟にも成るべし。 頌なるべし。
| 見聞した知識 |
摂州芥川は、水源は山州乙訓郡外田の山中より出、本山川と合て経て唐埼に至り、淀川に入る。 芥川村駅路有り。また、行事や伝承などにも詳しい。
昆陽野は、摂州阿辺郡寺本、池尻、山田等十四か村を都べて昆陽野と言ふ。 京より山陽道の往還にして、駅舎あり。
…
昆陽野浦の入江、今はなし。 昆陽野庄、古へは入江にして、西海に続き渡海の船往来す。 妓婦も有りたるなるべし。
正月初めの寅の日、毘沙門天、十種の福を与へ給ふ誓願有るに依りて、諸人群参す。「煎物」の祇園会(祇園祭)など。
祇園の祭礼囃子物の稽古の場へ、煎物を売りに行く狂言なり。 五月廿日より囃子初めと云ふてあり。 元日に檜垣の御茶屋とて、内裏えも入る。 荷ひ茶屋あり。 是等の類なるべし。「伯養」に出てくる座頭の納涼も、身近に見知っていたようである。
今、高倉通りの五条坊門の北に集会して、琴を弾じ、平家をかたる。「松脂」に出てくる松囃子は、当時も行なわれていたらしく、その作法が具体的に記されている。
松囃子と言ふて正月子の日に、丘に登りて四方を望みて陰陽の静気を得れば煩ひを除く。 また正月七日を用ゐる歳は有祝して松が枝を手折り、男は七本、女は十四本、此の義を以て松を詩に作り歌に詠み遊ぶ、仍て松をはやすと言ふ。「靭猿」の猿引についても、次のような記述がある。
紀伊国岸村に日本猿引の棟梁・貴志甚兵衛と云ふあり。 家景(家乗?)にいふ、其の先、小山判官政氏より出て、紀伊国に住すと云ふ。さらに、狂言に出てくる京都周辺の土地には、実見したところが多いようである。
通円、いつの比より始ると言ふ事さだかならず。 通円元は宇治の百姓にて、古河通円と名乗りしが、中絶す。 中興の通円より今の文政六(年)癸未までは廿代相続と言ふ。 … 今も宇治橋御普請の時、通円の居宅も御普請有り。 … 今の橋は仮橋なり。 通円が茶屋は東爪(詰め)にあり。「鬼のまゝ子」の印南野は、現在の兵庫県東播磨地方で、京都からは大分離れているが、実際に行ったことがあるようだ。
… 此の地、いま野中、清水有る所を証として、古へ曠野の様を見るに、明石郡の西より加古郡の東を掛けて二里計りの間を云ふべし。 今は新田にすきて人家も多し。 野谷野、寺野村など、みな野の字を冠らせて呼ぶなり。 …「磁石」に出てくる三河の八橋にも、行ったことがあるらしい。
八つ橋、三河国池鯉鮒(現在の知立)より八町東の方、牛田村の松原に石標有り、是より左りへ入ること七町、茲に一堆の丘山有りて、古松六七株、其の側に凹み成す地の形の芝生有り、是れ昔の杜若有りし所也。始めの方の「古松六七株、其の側に凹み成す地の形の芝生有り…」という記述が、その地を実見していたことを示している。 その後の、「八つ=弥つ」の考証もおもしろい。
<以下、伊勢物語の抄録 …略>
八つ橋の事は、諸説色々に、甚しきは大坂の四つ橋の様なる図を二つ書きたる説は論ずるに足らず。 すべて八は大数の程にして、皆十に満たざる物の数に用ゐる。 然れども伊勢物語にいへる八橋は、按ずるに更に八の字の義理なし。 八重霞も八雲もみな弥重(いやへ?=いくつも重なった状態か)なるべし。 八重桜、八重歯、みな弥重なるをもつてはかるべし。 八つの「つ」の字は助字にして、天津空、時津風、みな「つ」の助字と同じ。 又、弥の字に八つと書く法は併音とて、唐にも聖教賢伝に此の併音を用ひたり。 勿論、澤辺の水の交錯たるにより、橋の先にも橋をかけ、弥(イヤ)つ橋かけ渡せし故、誰言ふとなく弥つ橋と言ひしか。 地の字となり、いやのイ、発語なれば、やつ橋と言ふなり。
摂州天王寺郷に牛市とて、毎歳諸国より牛を牽て博労す。 今、石橋何某より牛博労の割(ワリ)符を出す。 古昔の遺風なりと云ふ。この記述だけでは、虎光がその地を踏んだかどうかはわからないが、次の「金津」の地蔵に関する記述をみると、やはり天王寺郷を訪れたことがあると考えられる。
摂州天王寺郷の中に、聖徳太子御作の地蔵有り。 毎年十一月十六日、此の石仏へ生鰯を供し、顔に米の粉を塗り、笹に蜜柑と煎餅を付けて供養し、同日夕方には藁に火を焼きて石仏を黒し、明年の明年のと囃し踊る出す。 その前に童ども道に縄を張り、お太子様の仰せぢゃ、天王寺のさほじゃさほじゃと云ふ。(天王寺の作法と云ふなり)もちろん、遠方の地には足を伸ばすことはなかったであろうから、大部分の情報は、人から聞いて得たものと考えられる。
信濃国安曇郡妻籠山中、冨士松と云ふあり。 冬は葉悉く落つ、夏木の松なりと言ふ。この冨士松は「からまつ」のことらしく、狂言の中の松と異なることは明らかであるが、名前が同じなので念のため記しておいたのであろう。
若狭国小浜めしの昆布、今も天目屋九兵衛にて製す。 一子相伝と云ふ。昆布を製造することを「めす」と言ったようで(「なめす」と同語源)、「小浜めし」とは小浜産あるいは小浜製の意味である。
入間川。 武蔵国多摩郡に有る川を玉川と云ふ。 六玉川の一つなり。 入間の里にては入間川と云ふ。 六郷の里にては六郷川と云ふ。玉川(多摩川)と六郷川は同じであるが、入間川は荒川に流入する川である。 別々の情報を結び付けたときに、誤解が生じたのであろう。
川嶋何某云ふ、東近江国大橋村と云ふ在所の神事に、どぢゃうのすしを備(供)ふること吉例なり。 鯲のすしを備へねば、神輿あがらずと云ふ。この川嶋という人は、虎光の身近にいた近江出身の情報提供者のようで、「い文字」の中でうたわれる歌についての情報も提供している。
川嶋何某云ふ、近江国日野の仁正寺に市橋公御成下の詞あり不詳。 此の所の祭礼に毎年此の謡を諷(うた)ふと云ひ、里童児まで諷ふと云ふ。「吃り」のところには、「伊勢水呑」の語について、伊勢の人に尋ねたことが記されている。
伊勢水呑と言ふは、土器の類などかと、勢州住の大久保何某え尋ねしに、いせ水呑と言ふ物、昔より知らずと言ふ。 今は二見が浦より出る貝あり、夫を旅人腰に付けて水呑に用ゆ、是を今、伊勢水呑と言ふと。 猶尋ぬべし。一応の回答を得ながらも、充分納得するに至らず、「猶尋ぬべし」としているところに、虎光のあくなき探究心が示されている。
| 実演に関すること |
文化年中、御本丸にて此の狂言何某相勤めし時、ばくち打ちと言ふこと御耳に障り、御尋ね有りし時、御側より当時御法度に相成り候ばくちと申す勝負事にて御座候由、申し上げられ候趣き、多賀大助殿より承る。 右に付き、已来(今後)成たけ翳(かく)し候方然る可しと承る。 往古より申し来りしこと、御耳に障り候儀は、其の仁の不幸なり。 … 予、「吃り」の狂言を三度続けて仰せ付けられし事あり。 「ばくち打ちの賽目ぎれ」と諷ひしかど、何の御沙汰もなかりし。「茶壷」の方では、「ばくち打ち」という言葉が繰り返されるので、「吃り」の場合に比べて、耳につくのかもしれない。
終