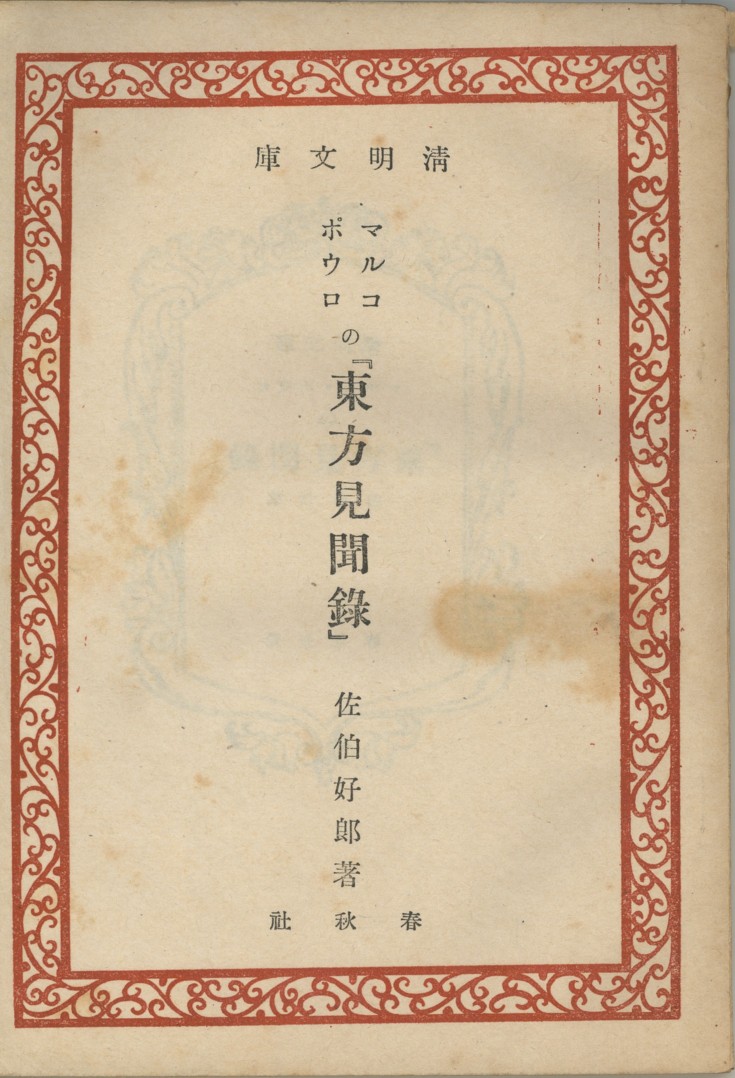
目 次
第一 『東方見聞録』著作事情
第二 マルコ・ポウロの『東方見聞録』と
他の欧州人の『東方旅行誌録』との比較
第三 『東方見聞録』について
第四 マルコ・ポウロの日本国に関する記事
及び元寇に関する記述等について
| らんだむ書籍館 |
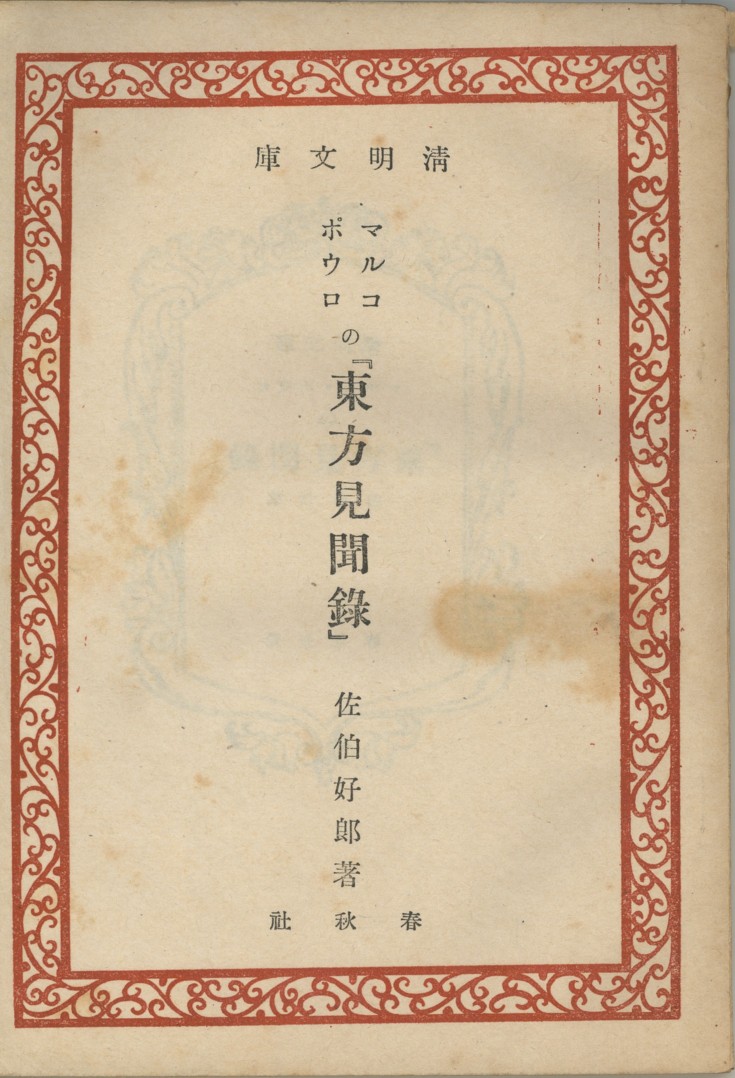
|
|
表紙 |
|
目 次
第一 『東方見聞録』著作事情 第二 マルコ・ポウロの『東方見聞録』と 他の欧州人の『東方旅行誌録』との比較 第三 『東方見聞録』について 第四 マルコ・ポウロの日本国に関する記事 及び元寇に関する記述等について |
| 本文の一部紹介 |
第四 マルコ・ポウロの日本国に関する記事及び元寇に関する記述等について
一 マルコ・ポウロの日本観
マルコ・ポウロは 我が大日本帝国に関して 真実と誤謬とを交へて述べて居る。 則ち
「 日本国( (日本国) ( の訛)は 支那大陸の東 一千五百哩の大海に在る 頗る大なる島国である。 その住民は白皙で 人智大いに開け 天恵を蒙ること多大である。 住民は仏教に帰依して居れども 全く自主自立にして 他国に服従するところがない。 この国に 無限無量の黄金がある。 その理由は この島国には黄金を産出すれども 国王、君主は之を国外に輸出することを許さないのみならず、大陸より遠く距たれたるを以つて 外国の商人もこの島国に到るものが無いから、黄金は無限に蓄積せらるるのみであるからである。)
この島国の君主の大宮殿が 全部残らず良質無比の黄金で葺かれて居る有様は、丁度 欧羅巴諸国で 教会堂の屋根が鉛で葺かれて居るのと 同様である。 故に これらの黄金作りの屋根を有せる宮殿の価値は 到底評価することは出来ない。 加之(しかのみならず)、大宮殿の敷石のあるべき所も、各室の床板のあるところも、石や瓦ではなく 全部とも悉く黄金の伸板で出来て居て、その厚さは 指二本の厚さである。 また宮殿の窓も 黄金作りである。 それ故に この日本国の富と宝とは 全く想像がつかぬほどである。
日本にはまた 真珠が沢山採取せられる。 その色は 薔薇色である。(モール版(1938年、英国 Moule-Pelliot社 出版の東方見聞録)は 白色、マルスデン版(1818年、英国 Marsden社 出版の東方見聞録)はバラ色) 美しい大きな丸形で その価値は白色に劣らない。 この島国では 死者を土葬にもし 火葬にもする。 火葬のときは 屍の口に真珠を含ましむるのが この国の習慣である。 この島には 真珠の外に多くの宝石類がある。
現皇帝 忽必烈汗(フビライ。1215~1294。 モンゴル帝国第5代皇帝にして、元朝初代の皇帝。 汗は王を表す称号。)は この島国に無尽蔵の富と宝とのあることを聞き、之を占領せんと決心するに至り 之を占領する目的を以つて、二人の将軍に 水軍及び歩軍及び騎兵に将として 遠征せしめた。 これらの勇将は アバガン(阿刺罕)と笵左丞( (笵文虎左丞)であつた。 両将軍は遠征軍を率ひて 刺桐城) ( 及び 臨安(行在)(杭州)湾を出発して 日本に向つた。 而して 日本に上陸して 海岸平原の三四村落を占領したが 都城を占領することは出来なかつた。 而して この遠征軍は 一大危難に遭遇した。 それは これら両将軍が不和で 相互に協力しなかつたことである。 また 偶々大暴風雨起り 暴威を振ひしが、この島国には良港がなかつたから 艦船は大搊害を蒙つた。 而して 忽必烈汗の艦隊は 全く之に堪へることが出来なくなつた。 茲に於いて両将軍は このままに放任しては全軍滅亡の外なしと思ひ 急ぎ還らんと欲した。 併し 全艦隊が四哩程進航して 一の小島〔鷹島かと思ふ〕に達したとき 大風のために、海岸に吹付けられて 艦船の大部分は難破して 軍兵の大部分は溺死してしまつたのである。 しかしながら 幸ひにして僅かに三万人が この小島に避難し得たのである。)
これらの避難し得たものも 食物が絶無であつたから 全く絶望に陥らざるを得なかつた。 丁度そのときに 難破を免れ得た元軍の艦船が、この小島に元兵が避難して居る事実を熟知しながら 少しも之を顧みずして 沖合を急ぎ帰国してしまつた。 これは 両将軍が不和であつたためである。 併し 若し帰国した将軍がこの避難兵を救助せんとすれば 容易に救助が出来たのである。 何故となれば この暴風も永続きせず、直に静まつたからである。 然るに 之を救助することをせずして 一人の将軍は急ぎで本国に帰還した。 しかし この無人島に避難したものはどうなつたのか、それを次に語らう 」
と結び、次章に於いて 「大汗日本遠征軍の其の後の運命」と題して マルコ・ポウロは
「 既に述べたるが如く この小島に残されたる三万人は 遁走の方法がないから 全く死を覚悟してゐた。 このとき 日本側の軍勢は、蒙古軍の一部がこの小島に打ち上げられてゐることを探知し、その水軍を以つて この小島を包囲攻撃し 日本側全部を上陸せしめ、愚にもその船には守備を残さなかつたから 蒙古兵は山上に遁るる真似をして 間道より下り 急いで日本側の船を乗っ取り 之に乗りて日本の本土に上陸し 人民、兵士を悉く打払ひ 美しき婦女のみを拉致して 我が物とした。 日本の側は 斯くの如く自国の艦船が奪取せられ 城邑の占領せられたるを知り 大いに意気阻喪した。 然れども 日本本土には他に未だ失はれない船舶があつたから、之を以つて蒙古軍が占領してゐた城邑を攻囲すること 七箇月に及んだ。 因つて蒙古兵は (一)生命の安全と (二)この島に滞在すること との二条件で 遂に日本軍に降伏した。 この出来事は 一千二百七十九年に起つたのである。 忽必烈は 逃れ帰りたる将軍を 死刑に処したのみならず、日本の小島に残留せる他の一人の将軍をも 死刑に処した。 蓋し 斯くの如き降伏は 忠勇なる兵士の恥辱なればなり 」
と 大嘘を述べてゐる。 更に 語を続けて
「 この日本遠征に関して 一の驚くべきことがあつた。 それは 忽必烈軍が日本本土に上陸し、城兵を鏖殺(オウサツ、皆殺し)したるとき、八人の日本兵は槍でも刃でも負傷しないことが発見せられた。 その理由は これらの日本の八勇士は その腕に或る種類の石を挿め込んでゐたためである。 而し この呪( の功徳によりて 弓矢刀槍では傷つけられないことが判明した。 因つて 蒙古の将軍がこれらの八勇士を撲殺せよと命じたるため 蒙古兵は之を撲殺した。 然るに 死後 これら八人の身体からこの石を取り出して 大いに珍重した 」)
云々と 信じがたきことを述べてゐる。
以上は マルコ・ポウロの記述の抄訳である。 彼が 欧州拝金宗国に生れたる支那出稼人であるだけに、第一、日本に無限無量の黄金が蓄積せられて居ることを喧伝した。 併し 日本に非常に沢山の黄金が存在して居たことは 徳川時代の外国人の記述にもある。 元禄年間の著作たるケンヘエル(Engelbert Kaempepfer,1651~1716。ドイツの博物学者。1690~92 オランダ商館付医師として日本に滞在。死後、日本に関する遺稿が「日本誌」として刊行された。)の日本歴史(前記「日本誌」の一部分)にも 多額の金貨が日本から欧州に輸出されたる事実が記してある。 それに拠ると 天文十八年〔西紀一五四九年〕から慶長元年〔西紀一五九六年〕までの約五十年間に亘り 毎年三百噸(トン) 約十二億円以上の黄金(金貨)が 西班牙(スペイン)、葡萄牙(ポルトガル)に輸出せられて居るとのことである。 これは 今日の政府御買上相場で見ると、約六百億円の金が日本から輸出せられたのである。 後に徳川幕府が 金の輸出を防止するため 鎖国政策を断行し、和蘭陀(オランダ)及び支那貿易を制限し、一箇年を金六十噸以下 則ち二億四千万以下にきり下げたのは、賢明な策であつたと思ふ。 兎に角、徳川幕府の初期までは 巨額の黄金が我が国に在つたことは 事実である。 併し 黄金作りの大宮殿の話は 誇大に失して居るが、斯くの如き誤伝が 忽必烈汗をして日本遠征の野心を生じせしめたことは 事実であつたと思はれる。 また 進取的欧州人を代表せるコロンブスが このマルコ・ポウロの記事を読んで 黄金作りの大宮殿を発見せんとして 米大陸を発見するに至つたとすれば、このマルコ・ポウロの記事は 之を咎めないでよいかも知れない。 乍併(しかしながら)、マルコ・ポウロの元寇に関する記事の不正なることは 決して黙許することが出来ない。 何故となれば 彼は 元の至元十二年〔我が建治元年〕 西紀一千二百七十五年頃に支那に到着し、元の至元十八年(弘安四年)〔西 紀一二八一年〕までには六年以上も北京に居たのであるから 決して斯くの如き誤謬の記事を残すことはない筈であるからである。 勿論、彼の述べて居る両将軍上和のことも 肥前鷹島で残兵が全滅したことも、笵文虎等が罪を獲て処刑せられたことも、大体に於いて 歴史上の事実に符合することと思ふ。 併し 日本に上陸し 七箇月も籠城して 条件付で降伏したなどと云ふことは 全く虚偽の陳述であつて 許すことは出来ないのである。 また 不死身石の話の如きは 既に一言したるが如く マルコ・ポウロよりも二十余年後に 南洋や南支那を旅行したるオドリック(本書の「第二」の部分に、その旅行記の簡単な紹介がある)も、南洋土人間にこの伝説があることを記して居る。 これが果たして 我が国の民間伝説となつて居る「不死身」と 如何なる関係があるか。 それは 他日の研究に俟つより外はない。
それは兎も角として、マルコ・ポウロが元寇鏖殺の事実を熟知すべき地位に居りながら 元軍の大敗とその後始末を一層明確に記述しなかつたことは 東方見聞録の記述の他の部分の真実性までも疑はるることとなつても 致し方がない。 これは 吾人が 東方見聞録のために最も遺憾とするところである。
二 元軍の武器 その他
この外にも一つ 東方見聞録の真実性を疑はしむる事項がある。 それは 元軍が日本に持ち来つて 我が将兵を悩ました武器の一つであつた 礮 (砲 の別体字。ここでは、投石機 をいう)の問題である。 〔マルスデン版 一四五章、モール版 一四六章、ユール版第二巻第三編七〇章〕 即ち、湖北省の要衝である襄陽は 南宋の他の城邑が蒙古に降伏しても 容易に降伏しなかつた。 それ故に 忽必烈は 至元十年〔西紀一二七三年〕正月に 襄陽の外郭たる樊城を陥れ、二月に至り 守将 呂文煥が 遂に襄陽を開城するに至つた。 この時は 至元八年〔西紀一二七一年〕に ニコラス・ポウロとマテオ・ポウロがマルコ・ポウロを伴うて欧州を出発して 支那に向つた二年後であり、三人のポウロが北京に到着したる至元十二年〔西紀一二七五年〕の約二年前であつた。 この旅行は途中が三箇年以上もかかつてゐる。 故に ポウロ三人は この樊城の陥落の時にも 襄陽開城の時にも 支那にはゐなかつたのである。 然るに 東方見聞録には
「 大汗の軍が襄陽を囲むこと 三年の久しきに及ぶも 城は陥落せず、元軍 之がために大いに焦慮す。 このとき ニコラス・ポウロとマテオ・ポウロ 並にマルコ・ポウロは 忽必烈に奏して 礮を製作して敵を破るべきことを 献策した。 当時 蒙古軍は 礮の製作方法も その使用方法も知らなかつた。 三人は 忽必烈より西洋式の礮の製作を命ぜられたるを以つて、ニコラスとマテオ及びマルコは 基督教徒である一人の独逸人と 景教徒の一人であるものとが、よく礮の製作法に精通せるを以つて 之をして三百斤弾丸を発するものを作らしめ 之を用ひて襄陽を陥落せしめた 」
とある。 併し この記述は、年代は勿論合致しないが 人物にも大なる誤りがあると思はれる。
通鑑輯覧に拠れば 「襄陽攻略戦は 至元五年〔西紀一二六八年〕九月に始まり 翌年〔西紀一二六九年〕正月、襄陽の師(軍隊)を益(増強)し、長囲を築き、久駐必取の基を立てた。 至元十年〔西紀一二七三年〕 元将 阿爾哈雅( は樊城を攻め 西域人の献ずる所の新礮法を得て 遂に外郭を破り、二月 之を移して襄陽に向ふ。 一礮、其の☐(?)楼に中(あた)る。 声 震雷の如し、城中恟恟、諸将 城を踰(こ)えて 下る者多し 」)
云々とある。 而して 通鑑輯覧の所謂(いわゆる) 西域人は マルコ・ポウロ等にあらずして、実に 「ダマスカスから忽必烈が招聘したる投石機製作技師のアブクルとイブラヒム及びマホメッドの三人 」の回教徒であつたのである。 彼らが多人数の職工を指揮して製作せしめたものが 新兵器の礮である。 而して 七基の巨大なる投石機を製作したるを以つて、忽必烈はことの外に喜び 之を襄陽の攻略戦に使用したといふ ラシッド・ウデンの記述に合致する。 而して この新礮は、其の後 数年にして 我が日本遠征にも使用したのであつて、元史は之を「回々礮」と書いてゐる。 故に この礮を忽必烈に供給したものは 回教徒であつて、ポウロ三人ではないやうである。 この一点は 他の「日本に関する誤れる記事」と共に 東方見聞録の重大な瑕疵であると思ふ。
三 マルコ・ポウロの漢字名
最後に一言すべきは マルコ・ポウロの元寇に対する責任である。 これは 彼の漢字名の問題で決するものである。 マルコ・ポウロは 支那に滞留すること 十七年余であつた。 而して 忽必烈汗に奉仕して支那の官吏ともなつたと ポウロ自身が記して居る。 何か漢字名があつた筈と思ふ。 併し我輩には 今日まで未だ漢字名を支那の文献中に発見し得ないことを遺憾とする。 例之(たとえば)、マルコ・ポウロが約三年間も 官職を奉じて居た地方たる揚州府誌にも マルコ・ポウロの名がない。 其の他 鎮江府誌にも 杭州府誌にも ポウロの漢字名らしきものを発見しないのである。 これは 尠からず マルコ・ポウロの東方見聞録そのものの、真実性を疑はしむるものである。 併し 自分が先年杭州で調査したところと マルコ・ポウロの記事とが 合致したるものが多かつた。 然るに 去今(今を去る)六十余年 仏国の東洋学者ポチエー博士は 元史巻九〔世祖本紀六〕の「至元十四年〔西紀一二七七年〕二月大司農御史大夫、宣慰使兼領侍司事「博囉」(孛羅)を以つて枢密副使となし 宣徽使を兼ね侍儀司事を領せしむ」とあるを材料として マルコ・ポウロが枢密副使となつた人だと発表した。 併し これは 今日から見れば 非常に軽率なる発表であつた。 何故となれば マルコ・ポウロは 父及び叔父と至元八年〔西紀一二七一年〕に欧州を出発して、而して 至元十二年〔西紀一二七五年〕に支那に来たばかりの新参者であつて、この問題の至元十四年には 未だ二十歳未満の一青年に過ぎなかつた。 忽必烈 如何にマルコを寵愛したりとしても 枢密副使の重職に任ずる筈はない。
元の枢密院は 参謀本部と軍務省とを兼ねたるもので、枢密副使は 参謀本部次長と軍務省次長とを兼ねたる重職である。 而して 忽必烈は 至元元年〔西紀一二六四年〕頃から 日本攻略の策を樹てて居た。 現に 忽必烈が至元八年〔西紀一二七一年〕に 趙良弼を遣した。 而して 至元十年〔西紀一二七三年〕 襄陽陥落のときの生券軍、即ち降参者を釈して 之を以つて日本征伐軍の急先鋒となし 日本に於いて乱暴を恣にせしむる準備をして居る。 故に 至元十二年に初めて忽必烈に謁したる一小輩マルコを、この重職に充つる筈はない。 また マルコの父のニコラスや叔父のマテオにしても、斯くの如き大任に就く筈はない。 何故となれば 彼等両人は 至元四年〔西紀一二六七年〕頃支那に来て、忽必烈の内命を奉じて羅馬法王庁に使してから 至元六年〔西紀一二六八~九年〕から至元十一二年〔西紀一二七四~五年〕頃までは 支那には居なかつた。 然るに 元史七巻〔西祖本起四〕 至元七年十二月 「司農司を改めて大農司となし 御史中丞博囉を以つて大農司卿を兼しむ」とある。 至元七年〔西紀一二七〇年〕には ニコラス・ポウロもマテオも 欧州に在つて 支那にはゐなかつた。 故に この博囉は ニコラスやマテオではない。 更にまた 程鉅夫の雪楼集に在る 拂林忠献王神道碑に
丞相博囉生吾土。 食吾禄。 而安於彼。 愛綏生於彼。 家於彼。 而忠於我。 相去何遠耶。
とある。 而して この文句は 至元二十一年〔西紀一二八四年〕 即ち元寇撃滅後四年目に 阿魯渾の朝廷に使して 遂に帰任しなかつた博囉のことを 忽必烈が歎息したるものである。 この博囉が 至元二十八年〔西紀一二九一年〕頃に 忽必烈の命により 元の公主を波斯に送つて 支那を去つて帰国したポウロ三人でないことは 明らかである。 果して然らば 元の世祖の参謀本部次長兼軍務省次官たりし枢密副使博囉は その職務上、弘安四年の元寇の役の責任者たることは明らかであるが、それが伊太利人のポウロでないことも明らかである。
乍併(しかしながら)、伊太利人ポウロ三人は 元史の博囉ではないにしても 彼等が多年忽必烈の朝に奉仕したことは事実である。 従つて 彼等が弘安四年の元寇に全然責任がないとは云へない。 現に 既に述べたる通り、マルコ・ポウロは 元寇の失敗を糊塗せんとするが如く 誤れる記事を書いて居るではないか。 而して 「以夷以夷」する支那の伝統的政策は 昔も今も変りはない。 明治二十七八年の日清戦の始めに 高陛号が撃沈せられると 独逸人軍事顧問フオン・ハンネケン(漢紊根)が飛び出し、後に 独、露、仏の三国干渉となつたではないか。 更にはまた 今回の日支事変の始めに当りて 我軍を苦しめたるものは かの軍事顧問のフオン・ゼークトが蒋司令の為に建設した ゼークト線ではなかつたか。 これらの吾人が既に知つてゐる事実から推測すれば、忽必烈が日本侵略を企つるに当り アラビア人、伊太利人、独逸人等を使用したところで 少しも怪しむには足らない。
結論として一言すべきは H.G.Wells が「支那の智慧負け」と評して居ることである。 即ち彼は 第五世紀以来、即ち 漢、唐、宋、元、明 は勿論、清の初期まで 支那が 学問、知識、生活、社会制度に於いて 欧州より遥かに進歩してゐたのが 何故に第十九世紀に入りてから進歩しないかといふ 一の問題に答へて、支那は支那の智慧で束縛せられたものだと 評して居る。 吾人を以つてすれば このことは大なる誤であると思ふ。
支那や東洋諸国が 第十九世紀に入りてから西洋に後れたのは 蒸気力機関の発明に基くのである。 一千七百六十九年以後のことである。 それまでは Handpower の時代では 東洋が西洋を指導してゐたのである。 我等は 蒸気力で後れたのであるのみだ。 しかも これを取戻す方法は 電気力にもあり 化学にもあることを 忘れてはならぬ。
終