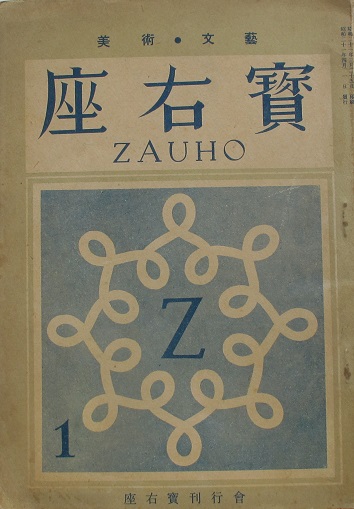

「新疆省喀喇和卓 唐時代高昌國人墳墓発見 木心女子土偶首部」
目 次
芸術雑俎 (1) 児島 喜久雄
美術雑感 武者小路 実篤
正倉院三彩 小山 富士夫
宗達・光悦私論 徳川 義恭
唐代木心女子土偶首部 熊谷 宣夫
|随 | 清長 長与 善郎
| | 今は昔 滝井 孝作
|筆 | 旧知 大久保 泰
志賀直哉への手紙 梅原 龍三郎
雪 (短歌) 斎藤 茂吉
小説 悪戯 (1) 志賀 直哉
編輯後記
口絵 (原色版) 旅順博物館 女子土偶の首
(グラビア) 石棺の彫刻とデッサン
オリンピアのアポロの臍
アポロとヘルメスの臍
ミロのヴイナスとアフロデイテの臍
梅・宗達
牛・宗達
ルソー
デユヒイ
