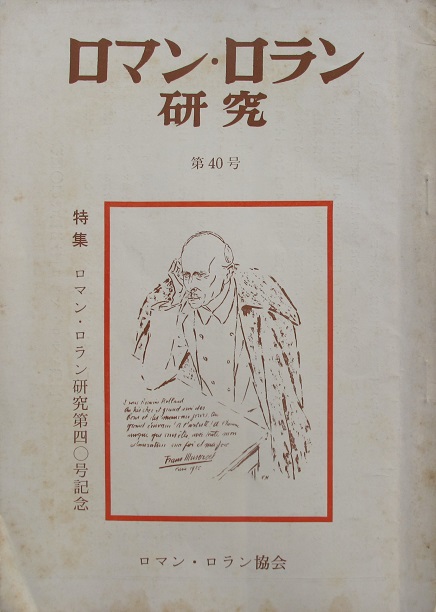
目 次
特集 ロマン・ロラン研究第40号記念
[未発表文献]
自叙伝のためのノート ロマン・ロラン
[フランス文芸批評界の第一人者による作家論]
ロマン・ロランの偉大さは永い忍耐にある クロード・ロワ
[日本人最初のロラン訪問記]
ロマン・ロオランの印象 成瀬 正一
オルガ山荘とロラン日記 中村 星湖
[討論]
革命劇「ダントン」をめぐって
窪村 義貫・大槻 統・青木 彰・辰濃 治郎
鈴木 崇・岸崎 隆生・川崎 輝子・小島 正喜
蜷川 譲・鈴木春香・山崎 実・牧田 美智子
表紙 フランス・マズマレールのデッサン