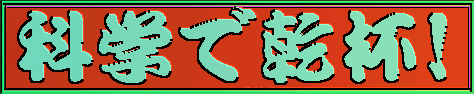
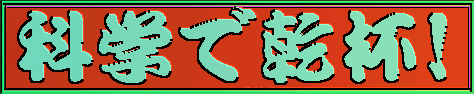
風来山人とは平賀源内(1728-1779)のことである。 当時評判の舌耕家(講釈師)深井志道軒(1677-1763)の冒険譚 というスタイルで世間の風刺を試みたものである。 志道軒の冒険は、大人国、小人国、足長国、手長国、穿胸国、及び女護が嶋を巡る設定で、 この点スウィフト(1667-1745)の「ガリヴァ旅行記」(1726)とよく比較される。 しかし、源内のこの作品での風刺は、政治に対する鋭い批判というよりは、 世間一般に対する苛立ちと言った方があたっている。
――世の常識ほど当てにならぬものはない。 人の善悪、事の良否に絶対的な基準はない。
勿論社会生活を営む上でのルールは必要であるが、 無批判に社会規範を受け入れることによる差別意識というものが
出来上がってしまっているのではないだろうか。 少し視点を変えてみれば、我々が善と思っていることが悪であるかもしれぬ。
幸せと思うことが不仕合わせかもしれぬ。 助けているつもりが大きな迷惑かもしれぬ。
今一度自分自身の力で素直な気持ちになって考えてみる必要があるのではないか。
この世に生きている限り、弱者というものはいない。皆対等である。 「生きている限り」という限定句さえ取り外して良いと思う。
「人はなぜ生きるのか」という問いは、「そこになぜ山があるのか」と問うのにも似た人の不遜が漂う。
宗教とは、人の存在に山の存在とは違った意味付けをするもののようである。
それはつまるところ、人が自然から突出したと自ら意識しはじめたところから
宗教が生まれたからである。 そして一旦宗教が形成されると、この自然からの突出が固定化され、
これを前提として規範が出来上がる。 それはやむを得ないことなのであろうか。
源内は生まれるのが早すぎたとよく言われる。 しかし、今の世に生まれたとしても、果たして源内は理解されたであろうか。
いつの時代に生まれたとしても同じなのではないかと私は思う。 それは源内にとって不幸なことであろうか。いや、それが源内の生き方なのだろう。