私のベンチプレス方法
私が採用しているベンチプレスの方法についてまとめてみました。14年かけて独自に考えた方法だったのですが、実はトレーニングジャーナル1986年10月号で解説されていたベンチプレスの方法と一緒で、一般的な方法だったようです。方法自体には自信がついたのですが、ちょっとがっかりしました(^_^;。
参考資料:トレーニングジャーナル 1986年10月号(62〜67頁)
(説明図については、この記事から一部を引用させていただきました( ^.^)( -.-)( _ _))
目 次
- はじめに
- ヘビーウェイトに耐えるフォーム
- 伸張反射の利用
- パワーリフティングへの適用
はじめに
ここで紹介するベンチプレスの方法は、全身のしなりを利用する方法であり、どちらかというと上級者向けの方法ということになります。初心者の方は、まずはベンチプレス自体に慣れて神経系を整備し、限界まで追い込めるようになる必要があります。その後に、記録が伸び悩む時期がきたときには、ここで紹介する方法が壁を破る助けとなるかもしれません。また、このフォームではパワーリフティング大会では失格となってしまいますので、大会へ向けての調整が別途必要となります。
ヘビーウェイトに耐えるフォーム
ベンチプレスの記録を伸ばすためには、肩関節を痛めないようなヘビーウェイトに耐えうるフォームをマスターする必要があります。
- 肩関節の固定
- ベンチプレスの際には、肩関節が動くことから、肩関節を固定することが重要である。
- ベンチプレスの主働筋は大胸筋(胸)、三角筋(肩)、上腕三頭筋(腕)であり、拮抗筋は広背筋、大円筋、棘下筋(すべて背中)である。肩を固定するためには、拮抗筋を同時に作用させて、上腕骨の先端を肩関節内にしっかりと固定する必要がある。
- 下図のように、肩を回外した状態で固定することがポイントである。(肩甲骨を寄せるとともに、脇をしめるようにする。いわゆる『横の締め』)
- また、みぞおちを持ち上げるようにして胸を張ることによって、荷重の真下に肩関節を置くことができ、安定してバーベルを支えることが可能になる。(いわゆる『縦の締め』)
- 以上の動作によって形作られるフォームが、いわゆる『ブリッジ』と呼ばれるものである。お尻はベンチ台に触れる程度にして、脚と肩でブリッジを組むようにすると、脚の力まで利用した全身のしなりを使った動作が可能となる。
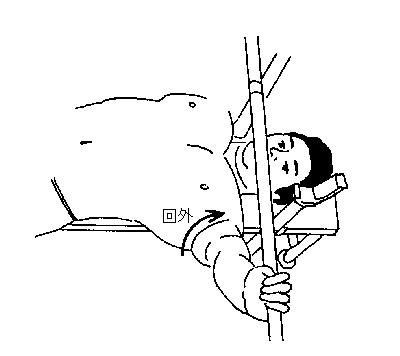
- バーベルの挙上動作
- 主働筋、拮抗筋に均等に力が加わった状態でバーベルを胸まで降ろす。
- 胸を上方へ突き出すようにしながら、脚、腹、胸、肩、腕と順番に力を伝えてゆく感じで一気に力を加えて挙上を開始する。
- この挙上動作において、全身のしなりを用いることによってより大きな力を発揮することが可能となる(後述)。
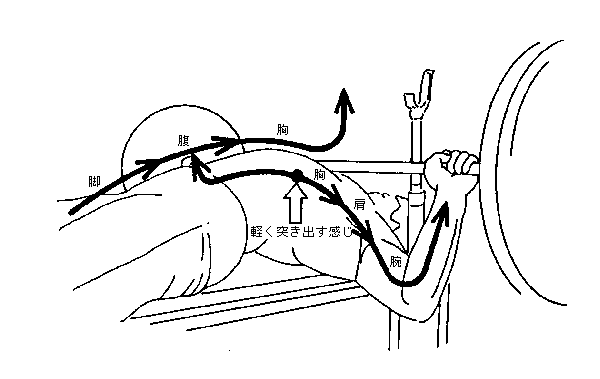
伸張反射の利用
挙上開始時に全身のしなりを使い、主働筋の伸張反射を用いることによって、より重い重量を扱うことができるようになります。動作の流れは下図の通りです。
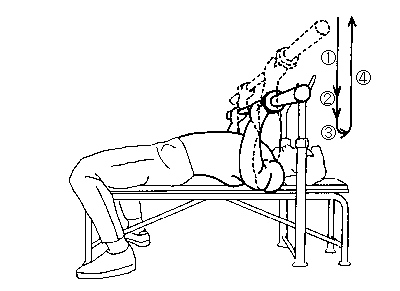
- コントロールしながらゆっくりと降ろす。
- 一瞬力を抜いて、バーベルを降下させる。(5cmくらい)
- バーベルを受け止めるように努力する。ここで伸張反射が発揮される。
- 伸張反射の力を利用し、主働筋の全運動単位を一気に点火するつもりで、爆発的にできるだけ高速に挙上を行う。
全身のしなりを使うイメージですが、私は脚先を起点としたムチが胸の部分でバチッとしなる感じを思い描いています。ちょっと練習しないとタイミングがずれてしまうのですが、調子が上がってくると面白いくらいにバーベルが軽く感じてきます。ディップスをするときに、ボトムポジションで反動を使うのと感覚が似ています。補助トレーニングとしてディップスは欠かさず行っていますが、ディップスが滑らかにできるようになってくると、ベンチプレスに調子も上がってくるようです。
挙上時に伸張反射を用いることから、反動を使わない場合に比べてより重い重量を扱うことができますが、これは降下に最大挙上重量を超える負荷でネガティブ(エキセントリック動作)を行っていることになります。筋力、筋量アップに効果が大きかった原因は、このあたりにあるように考えています。
しなりを用いると、必然的にお尻がベンチ台から離れます。しかし、普段の練習ではより重い重量を扱って筋力、筋量アップをすることが重要ですから、この点については無視して良いと考えています。練習によって貯えた筋力を、パワーリフティングの大会で発揮するためには、調整期間が必要となります(後述)。また、ブリッジで腰を痛める場合というのは、お尻を高く上げた状態を続けた場合に発生するようです。お尻を上げる動作は、あくまで伸張反射のきっかけとなるものであり、バーベルを受け止めて挙上を開始する瞬間のみとして、その後にはお尻の位置を元の状態に戻せば、腰を痛める可能性が低くなると考えます。移動距離を小さくするためにお尻を浮かすのではないことに注意する必要があります。
パワーリフティングへの適用
パワーリフティング大会では、胸の上で静止させること、またお尻をベンチ台から離さないことなど、上記の練習とは異なるフォームが要求されます。私の場合、以下のようにして調整しています。
- 大会2週間前から2回程度、大会フォームでベンチプレスを行います。軽い重量でしっかりとフォームチェックを行った後、第1試技で挙げる予定の重量まで挙げてゆきます。ここでは絶対につぶれないように気をつけています。悪いイメージが残ることを防ぐためです。
- 脚と肩でブリッジを支えるフォームは変わりません。お尻はベンチ台にちょこんと触る程度にします。こうすると脚の力を使うことができます。思いっきりしなりを使うわけではありませんが、しっかりと脚でブリッジを支えることによってより重い重量を扱うことができるように思います。ここからは私の推測なのですが、ごく小さな反動を無意識のうちに利用できているのではないかと考えています。
 ココをクリックすると私までメールを送れます。
ココをクリックすると私までメールを送れます。
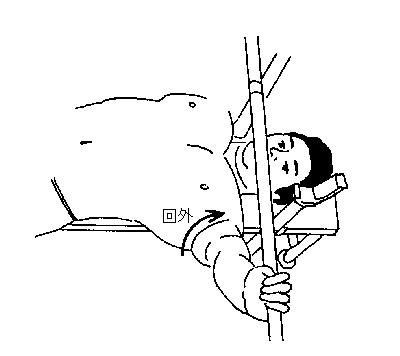
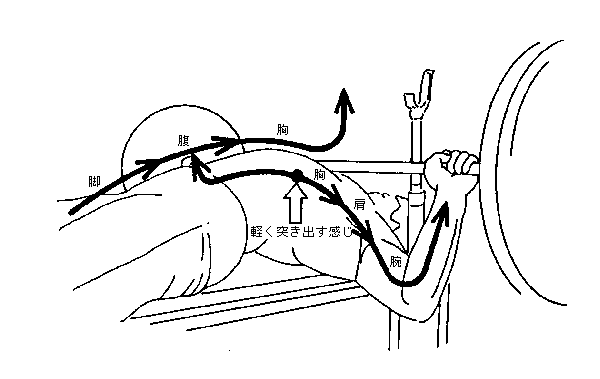
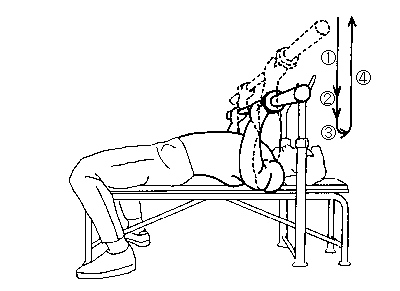
 ココをクリックすると私までメールを送れます。
ココをクリックすると私までメールを送れます。