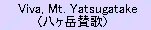 |
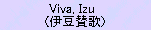 |
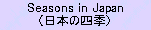 |
|
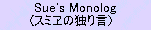 |
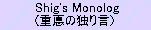 |
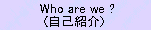 |
|
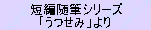 |
 |
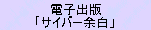 |
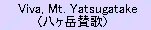 |
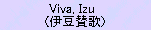 |
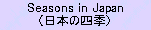 |
|
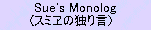 |
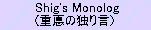 |
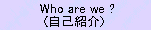 |
|
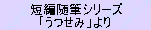 |
 |
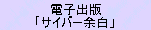 |
面白い表題の本があることを知って買ったが、それほどでもなかった。
「稼ぐ人 安い人 余る人 キャメル・ヤマモト 幻冬舎 2001/9 p262」
これからの会社員にはこの3種類があるというのが、筆者の見解である。本名山本成一。1956年生まれ。東大法学部から外務省に入ったが思うところあって退職しコンサル会社に転職、Silicon Valleyに住む。実は私はこの3種類の背景や分析が読めるかと表題から期待して興味を持ったのだが、内容のほとんどはどうすれば「稼ぐ人」になれるかという現代サラリーマン道の本だったので、私としては興味を失った。しかし21世紀のサラリーマン道を極めたいと思う人には読みやすくインパクトのある良い本かも知れない。いずれにせよ表題は気に入った。
「稼ぐ人」は会社のために金を稼ぐ人で、自分の稼ぎも良い人だ。何らかのタレントであり、命令されなくても行動規範が無くても自分で考えて自律的に動ける人だ。非定型業務を担当し、あるいは非定型業務を定型化して「安い人」に作業させる人だ。Computer Systemや作業手順を作り出す人かも知れない。
「安い人」は、低賃金で定型的な仕事をこなす人だ。企業はできるだけ安く使うためにパートタイマや外人労働者を使ったり、外国の工場でモノを作ったりする。ハンバーガ店の接客員や製造ラインの組立工はこのカテゴリーに入る。作業マニュアルがしっかりしていることで知られている企業、例えばディズニーランドTDLやSeven-Elevenの従業員はアルバイトが多い。知らなかったのだが銀行などの金融機関でも窓口に立つ人は今やほとんどはパートタイマで、正社員は後方作業をしているのだそうだ。昔は一番優秀な美人を最前列に並べたものだが。定型的な仕事の一部はComputerでもやれるが、仕事によっては人の方が安かったり都合が良かったりするから「安い人」の仕事がある。
企業が必要とする人材は上記の2つに大きく分化し、中間的な存在は居場所がなくなり、「余る人」になる。Computerあるいは「安い人」と同じ仕事をしているのにコストが高い人である。「稼ぐ人」のつもりで一向に業績が上がらない人も余る。伝統的な日本の企業では、終身雇用・年功序列のお陰でそこそこにやっていれば勤務年数に応じて給料が上がり、しかも専門性よりも協調性や長年の人付き合いが重要視される結果、企業の外に出ると途端に何の役にも立たない高給者が量産される結果になっていた。つまり伝統的な日本企業は「余る人」の大量製造装置の役割を果たしてきたと私は思う。
米国のベンチャ企業に勤めた経験では、会社には「稼ぐ人」しか居なかった。むしろ「一杯稼ぐ人」とか「やや稼ぐ人」とかの色模様だった。それは当たり前で、もし稼がない人が居ればクビにすればいいのだから話は簡単だ。強いて言えば秘書や受付・交換手が「安い人」だったのかも知れない。日本では女性の高給職である秘書職も、米国ではトップの秘書を除く一般秘書は安い職種の一つである。もし製造現場を持つベンチャ企業だったらもっと多くの「安い人」が工場に居たに違いない。
なぜこのように変わり、二極化してしまったのだろうか? 工業化時代には協調的な均質の人材が必要だったのだが、脱工業化時代では独り狼的で創造的な個性派が必要になってきた、というのが一点。Computerを代表とする自動化技術が進んできて、伝統的な人間の領域が犯されてきたという理由もある。経済が国際化して日本流同士の競争では済まなくなり、否応無しに外国特に米国と中国の影響を強く受け、安さも含めて何が特徴なのか、何をセールスポイントとして会社生活を送ろうとしているのかが厳しく問われる時代になってきたという事情もある。
そこでふと思った。個人レベルだけではなくて、組織レベルや企業レベルでも同じ構造で「稼ぐ組織」や「安い企業」がある。「余る会社」は退場していくことを迫られる会社であろう。そこそこの組織や企業は要らなくなって来ているのだ。個人であれ組織であれ、願わくは余る方ではなくて稼ぐ方でありたいものだ。 以上