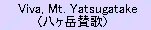 |
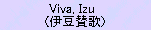 |
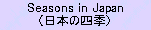 |
|
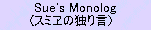 |
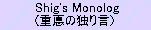 |
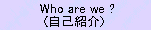 |
|
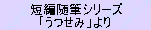 |
 |
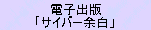 |
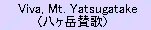 |
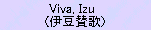 |
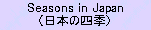 |
|
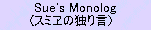 |
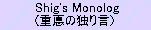 |
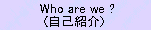 |
|
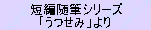 |
 |
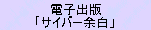 |
6月23日の英国民投票で国民の51.9%がEU離脱を選んだ。David Cameron首相や世の識者と同様に私も、英国民は最終的にはEU残留を選ぶに違いないと信じていたから大いに驚いた。投開票の3日前私は珍しく或る小さな講演をしていて、自信たっぷりに「英国民は馬鹿ではないから残留になる」と言い切ってしまった。拮抗していたが、最後まで世論調査に上がって来なかった浮動票が雪崩を打って離脱に流れたという解説を聞いた。
今手元に2026年の英紙Financial Timesがある(妄想!!)。"That's why we should have left EU"(だから離脱しておけば良かったんだ)という市民の声を見出しとして伝えている。見出しのようなEUへの不満を依然抱えながらも、結局英国は10年経っても離脱しなかったのだ。Cameron首相は開票結果を受けて「離脱手続きは9月に任命される後継者に任せる」と宣言した。離脱を主導したBoris Johnson元London市長が首相に選出されると当初予想されていたが、ポンド下落の中で熱気が収まってみると、米のTrump氏に似たJohnson氏の風貌と言動が議員と市民に危惧を呼んだ。結局残留派ながら残留・離脱どちらの旗も振らなかった穏健派の内相(Home Secretary)Theresa May女史が、残留派が多数を占める議会で、離脱派からも或る程度の理解を得て、首相に選出された。
国民投票の結果に法的な強制力は無いが、Cameron首相が結果の尊重を公約したのを尊重してMay首相は「離脱省・離脱委員会」を組織し、どう離脱すべきかを検討させた。委員会は拒否するEUと秘密裏に接触しつつ離脱方針を検討したが、他国の追随を恐れるEUは英国に甘い条件を許容せず、離脱委員会は揉めに揉めた。2017年末に委員会がやっと玉虫色の結論を出した頃には、(1)離脱派が語っていた甘い夢は実現不可能と知れ渡り、(2)英国経済は見通し不透明から低迷し、(3)英経済界から離脱のリスクが現実味を以て語られ、(4)Johnson氏の離脱運動は首相の座への野心からと信じられるようになり、(5)残留が優勢だったScotlandとLondon市とで再度の国民投票の要求が強まった。EU基本条約第50条に基づく公式の「離脱意図通知」をEUに出すことは残留派が多数の議会で承認されることはなく、従って通知があってから2年間で行われる公式の離脱折衝は、遂に行われることなく10年経過してしまった。という経緯が妄想紙面に回想してあった。だから私の講演は10年後で見れば間違いではなかった。
現役時代に毎年労使間でボーナス交渉が妥結すると、労働組合員は妥結内容に関して賛否の集約投票をした。各管理者は総務から、集約投票の賛成率を上げるよう組合員に働きかけることを要請された。ボーナスの賛成率の低さは、不満を抱く社員の多さを相関高く表すという。不満とボーナスの関係の有無に拘わらず、例えば職場環境への不満であってもだ。各管理者は、自分の職場が不満だらけの職場と見なされぬよう努力した。
英国民投票も同様で、離脱派勝利の背景には、現状への不満があったと言われる。生活に不安や不満があると、その原因がEUに関係があっても無くても、現状に反対する投票が増えるという原理は理解できる。最後まで態度を決められず世論調査に上がって来なかった層は、教育レベルが比較的低く概して低収入で、EUがあっても無くても押し寄せた経済国際化の波に洗われた不満分子で、反体制派の扇動に乗り易かったのであろう。
同様な不満分子に支持されているのが、米国のTrump現象、仏のLe Pen現象である。日本では不満を正面からスローガンに拾い上げている共産党が選挙の度に票を伸ばしている。かって独国民は、第1次大戦敗戦後の混乱した社会から、不満のエネルギーでHitlerを独裁者に仕立て上げた。
国論が二分する場合、具体施策の国民投票はえてして国の将来を誤る。選挙民も勿論ピンキリだが、選挙民全体を1人の人格に例えれば、選挙民は論理的であるよりも感情的で、長期視点よりも短期視点で行動する。
TPPでも安保法制でも原発再稼働でも「民意に百%従うのが理想的な民主主義」と信じている人が少なくないが、民意のままにしたら国が成り立たず、国民を不幸にする。それでもやるべきことと民意との間に妥協線を求めて行く過程で、民意は百%ではないが相当程度活かされていく。以上