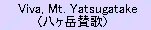 |
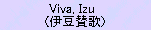 |
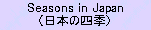 |
|
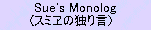 |
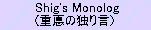 |
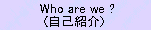 |
|
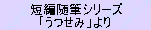 |
 |
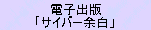 |
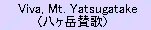 |
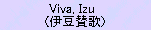 |
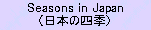 |
|
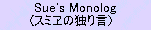 |
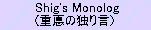 |
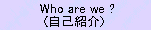 |
|
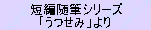 |
 |
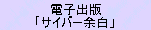 |
世界を砂の文明、石の文明、泥の文明と3分類する説を面白く読んだ。
「砂の文明・石の文明・泥の文明 松本健一 PHP新書 2003/10/31」
著者は1946年生まれ、東大経済卒、元京都精華大教授、麗澤大教授。
砂の文明とは勿論砂漠の遊牧民の文明で、その多くはイスラム教地域である。石の文明は、岩盤上の薄い表土で牧畜が行われる欧州と、そこから派生した米国の文明である。石造建築が特徴だ。泥の文明は、分厚い表土が緑豊かな環境を形作るアジアの文明である。
世界を旅行した後に日本に戻って来て、緑の木々に恵まれた日本の風景を眺めながら成田に近付く時、慣れ親しんだその風景が世界的視点では稀とは言わぬまでも珍しい存在であることに気付いて「懐かしい母国」という感慨が湧く。何十年前まで日本では、塀は土塀、壁も塗り壁だったし、農家育ちでもない私ですら子供の頃、田んぼの泥に膝まで足を取られながら田植えをした記憶がある。確かに泥の文明とはよく言ったものだ。
著者は今世界中で緊張の舞台となっている砂の文明から取り上げている。サラサラの砂がどこまでも続く砂漠や、カラカラの荒地である沙漠では、ほとんど価値を生まない土地を所有することは無意味で、従って私有地や国境は本来意味をなさない。大事なのはどこにオアシスがあるとか、どこに何を運べば商売になるかなどの情報や交易権であり、情報を運んでくれる人的その他のネットワークだ。砂漠の民が客人を大切にするのは情報を運んでくれるからだという。独立独歩で規制や強制を最も嫌う人達である。アラビヤやモンゴルで遊牧民を定住させようと近代設備の集合住宅を建てて収容しても、すぐ逃げ出してしまうのだそうだ。また厳しい自然と対峙する中で一神教が生まれ易いともいう。
欧州でなぜ石造りの家が多いのか、気候の他は深く考えたことがなかったが、言われてみれば確かに木材より石材の方が豊富なのだ。思えば森が豊かな南独の伝統建築は木造だ。欧州は氷河期には氷河にスッポリ覆われていた地帯だから、岩盤に至るまで削り取られてしまった。暖かくなってから日が浅く表土の発達が進んでいない。南欧を除く欧州の大部分では、薄い表土の下はすぐ岩盤なのだ。だから木々が育つことなく牧草地になっている。岩を積み上げた塀で囲った牧場に牛や羊が群れているのは、欧州では見慣れた光景だ。著者はそこで面白い理論を展開する。一つの家族を養うには牛百頭が必要で、それには3万坪の牧草地が必要だそうだ。そういう牧畜業の家族がより良い生活を求めたり、複数の子供に相続する場合には、広い新たな牧草地が必要になる。この伝統が石の文明に外部進出・開拓指向という特徴をもたらしたという。ローマ帝国拡大の歴史も、大航海時代、植民地時代、西部開拓時代などのフロンティア精神もその延長線上だという主張だ。自然が豊かでないだけに、自然は変えるべきものという立場から自然科学が発達し、自然を尊重し利用させてもらう泥の文明と対照を成す。全てをそれに帰するには無理があるとしても、大きな影響のある要因だと言われれば十二分に納得できる。
泥の文明では、豊かな泥の中から価値が次々に生まれてくる。その意味で本質的に多神教の土壌だと著者は言う。旧約聖書創世記では神が世界と人を作るが、古事記ではドロドロの沼地の自然から次々に神が生まれ人間の先祖となる。生産性の高い土地だから古来人口密度が高く、自分の田畑の隣や周辺には必ず他人の田畑があり、限られた開拓の他には拡張はままならない。従って生活向上のためには同一田畑の生産性向上しかなく、しかもそれが可能である。このため泥の文明では内向きの改良改善指向が強いと著者は言う。石の文明が生産手段の発明に指向するのに対して、泥の文明では生産過程の改善を得意とするという主張である。定住性の強い泥の文明では相互扶助が発達し脱落者を許さない。その代わり自分勝手も許さない規制指向があるという。これも確かに説得力がある。
泥の文明では県境や国境は自然に従った曲線で、石の文明では人工的な直線が多用され、砂の文明では強いて言えば点線という対比も面白い。
こういった視点で見たことが無かったので、大変参考になった。 以上