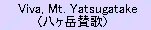 |
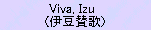 |
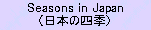 |
|
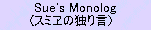 |
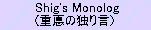 |
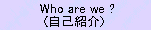 |
|
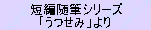 |
 |
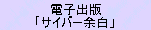 |
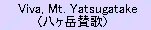 |
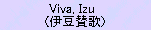 |
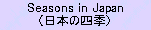 |
|
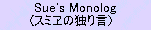 |
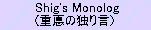 |
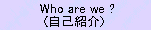 |
|
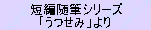 |
 |
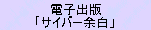 |
デフレとは、「柱」のようなものだとか、「ホース」のようなものだとかの諸説の中で、やっと「象」の全体像を解説する本に出会った。デフレだけでなく近代の経済現象全般を読み解くバイブルのような本だ。
「100年デフレ 水野和夫 日本経済新聞 2003年2月 pp385」
三菱証券理事チーフエコノミストの著者は、このデフレは世界規模で100年続くという。飛びがちな論理が難解な本だ。数式が多く微分まであるが読み飛ばしても文脈は分かる。著者の武器は(1)計量経済学と(2)歴史データ・視点だ。全体の2割強79頁の引用文献リストが著者の勉強量の証だ。
デフレは、(1)14C(14世紀の意。以下同じ)初めから15Cの150年(モンゴル帝国瓦解で貿易縮小)、(2)17C初めから18C半ばまでの150年間、(3)19C初めから19C末までの80年間(産業革命の技術革新と、欧と米の市場統合)、そして(4)今回は1994年に始まって100年続くと著者は言う。環境が(4)と似ているのは(2)だそうだ。17C初めの先進国はスペイン帝国とイタリアで、後進国がポーランド・ロシアなどの東欧だった。欧州市場は細分化していて、小麦粉の価格は6-8倍違っていた。150年の間に経済の中心が北のオランダ・イギリスに移行する過程で欧州市場が統合され、小麦粉の価格差は2倍程度に圧縮された。価格の平準化で先進国の物価が低下したのは当然だが、後進国の物価も一旦急上昇したあと1660年頃から下がった。価格上昇による増産の反動で、これがデフレ(2)の本質だそうだ。
上記(4)では、1994年以降欧米と日本で一斉に物価上昇率の低下が見られるという。上記(2)と似たところだが、中国や旧共産圏を含む第三世界が世界経済に取り込まれ、先進国の物価が低下した。第三世界の物価は上昇したが、やがて下がり始めるというのが歴史の教訓だそうだ。21Cがデフレの世紀になるという論拠を著者は3つ挙げている。(a)上記のような世界市場の統合、(b)最高技術と最低賃金(例えばシリコンバレーとインド)がIT技術のおかげで結合、(c)中国などアジア諸国の為替レートが数倍過小評価のまま世界市場統合に入ってしまった、ことだという。
貿易で価格が平準化される製品に対して、サービスなど非貿易品の価格は概してGDPに比例し、しかもGDPが大きいほどサービスの占める割合が大きい。だからGDPが大きいほど平均物価は高くなる。各国のGDPと物価をグラフにすると、大体一直線上に並ぶが、日本だけは例外で飛びぬけて物価が高い。つまり内外価格差が例外的に大きい。原因は非貿易品に業界保護の様々な規制があり、自由な競争ではないからだという。しかし世界市場統合と規制緩和が少しずつ進み、非貿易品も徐々に国際競争に晒されてきた。例えばインターネットのおかげで日本の英会話教室の先生が米国に居ることが可能になり、またソフトウェアの制作作業も外国に出すようになった。そうなると先進国の中では日本が飛びぬけて強い物価低下圧力を受ける。歴史に学べば、今後100年間不可避的にデフレに晒されるはずの各国の中で、日本が先頭を切っているのはこういう理由だそうだ。
資産が大して無かった時代には、通貨量を増せば物価は上がったが、近年は通貨量を増しても資産価格が上がるだけで一般物価への影響は減少したそうだ。しかも世界金融市場の統合で、日本が通貨量を増しても日本の資産価格が上がるとは限らず、世界の資産価格に薄まってしまうという。日銀が通貨量を増しても一般物価には影響せず、例えば日本人・日本法人の在米資産が増え、需給関係で米資産価格が上がるという訳だ。
著者はデフレで何が困るんだ、困る人もいるが一般国民にとってはデフレも悪くはないんだ、100年間共存しようと呼びかける。しかし一方でバブル崩壊が実は20C型経済の終わり21C型経済の始まりだという認識が世の中に無く、政治にもなく、土地本位制が国債本位制に変わった程度で国民国家に最適な20C型経済を何とか維持しようとしていると、世界の工場中国と、世界の金融帝国米国の間で日本は立ち往生すると警告している。
デフレの原因は、中国価格や、日本の在外資産だとする説や、実力以上の円高だとする説などを今まで読んで、成る程と思ったが、この本の主張の一部に位置づけられる。つまり「象」の足や鼻に相当する。 以上