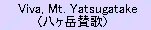 |
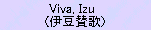 |
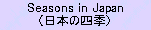 |
|
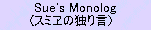 |
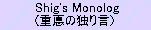 |
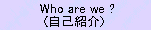 |
|
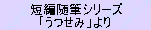 |
 |
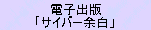 |
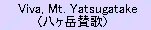 |
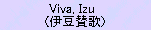 |
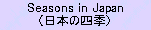 |
|
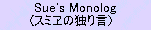 |
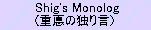 |
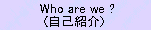 |
|
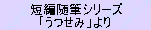 |
 |
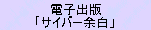 |
夏目漱石は、Unconscious Hypocriteを描くと言って里見美彌子を書いたという。東京帝国大学講師、第一高等学校教授を辞し、朝日新聞に入社して文筆活動に専念するようになった漱石は、小説「虞美人草」に続いて「三四郎」を1908年に紙上連載した。小説の主人公は勿論、熊本の第五高等学校を卒業して東京帝国大学文学部に入学したばかりの「小川三四郎」で、舞台は漱石が勝手知った20世紀初頭の大学構内と本郷界隈だ。大学の「三四郎池」はこの小説に由来している。当時まだ帝国大学は東京・京都・仙台の3校しかなく、三四郎は間違いなくエリートだった。正門から入ると、銀杏並木と両側の法文の教室があるが、1925年竣工の安田講堂はまだ無く、真っすぐ坂を下って理科大学に至ると書いてある。
上京してすぐ三四郎は同郷の野々宮先輩を研究室に訪ねた後、三四郎池の北端に今も茂る椎の大木の下に佇む。左手の小高い丘に、大学病院に見舞いに行った帰りの里見美彌子が看護婦と共に現れ、団扇(うちわ)で眩しさを避けながら夕日に向って立つ。この絵のような風景が最初の出逢いだ。美彌子は丘を下って三四郎の前を通り過ぎる時、手に持った白薔薇をわざと三四郎の目の前に落として行く。美彌子が野々宮と付き合いがあった関係で、三四郎と美彌子の付き合いはその後深まって行く。
小説の著者は、描きたい人物を主人公に据えることが多いが、漱石が本当に描きたかったのは美彌子ではなかったかと私は思う。三四郎の恋を通して美彌子を描いている。魅惑的でユニークな人柄だ。勿論美彌子が美人でないと小説にならないが、当時もてはやされた古風な細目の弥生系美人ではなく、二重まぶたの目が大きい縄文系美人として描かれている。地方の良家のお嬢さんで、法学士の兄と本郷に住む。当時としては稀有のことだが、英語に堪能なインテリで、誇り高いモダンな女性だ。三四郎は一目惚れしてしまう。二人だけの何度かの機会にその恋は益々高まっていく。美彌子は、ある時は彼を誘い、彼の恋が高まると冷たく突き放す。三四郎は美彌子の心を図り兼ねて翻弄されてしまう。最後に美彌子は、「我わがとがを知る」と詩篇の一節を呟いて立派な紳士と結婚してしまう。
美彌子は三四郎が好きだったはずだ。絵のモデルになるよう頼まれた時彼女は、最初に三四郎に会った時の団扇をかざした姿を望んで描いてもらった。しかしまだ大学に入ったばかりの三四郎との結婚はあり得ないという現実も一方にはあり、迷える羊Stray Sheepを自称していた。 それがなぜUnconscious Hypocriteなのか? まずHypocriteは、一般的な意味の「偽善者」ではなく、より原義に近い「演技者」と解釈しなければならない。美彌子は三四郎が好きなので、無意識のうちに自然に三四郎の関心を得るような行動をとってしまう。しかし結婚適齢期の彼女には或る一線以上には踏み込めないところがあり、自然に突き放す行動にもなる。その振幅が三四郎を悩ませる。
小説「三四郎」を読み返す度に私は幼馴染の或る女性を連想する。小学4年に転校してきた美少女は、中学高校のマドンナになった。中学では私と総合成績を競った。音楽・体育・書道で大分努力した私が最後には勝ったがしばらくは負け続けていた。グラウンドでは私は野球とリレーの末席選手、彼女は排球とリレーの花形選手だった。我々凡人は、自分に好意を持つ人や持たぬ人が混在する社会で育つ。しかし彼女はモテ過ぎて育ち、周囲全員から憧れられていないと不安だったのだと思う。だから心の離れた人が居ると関心を釣り、しかし特定の人と特に親しくして他の人の関心が遠のくことを極端に恐れた。悪意や作戦でそうしたのではなく、やや特異に育った性格のままに自然に無意識にそうしたようだった。だから周囲からすると、気のある仕草で釣られ、その気になると突き落とされた。
彼女に限ったことではない。美彌子に限る訳でもない。実は女性とも限らない。男性でも努力のストレス無しに極く自然に上司にオベッカを使う人が少なくない。騙されまいぞと会社で身構えた記憶もある。
或る割合でUnconscious Hypocriteは居るものだ。しかし同じなら、美彌子のような魅力的なUnconscious Hypocriteの方がいい。 以上