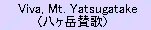 |
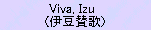 |
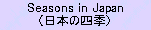 |
|
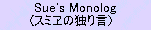 |
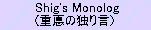 |
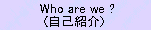 |
|
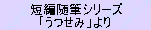 |
 |
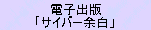 |
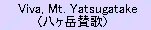 |
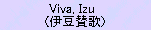 |
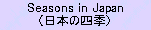 |
|
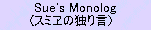 |
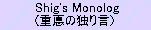 |
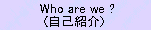 |
|
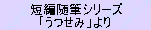 |
 |
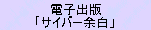 |
今回読物として「斉藤茂吉著 万葉秀歌上下 岩波新書」を持ち込んだ。万葉集20巻には5世紀末から8世紀末までの4,500首の詩歌が集められているが、そのうち短歌が4,200首あって、その約1割を筆者が選んで詳細に解説したものだ。この本は岩波新書の創設と共に昭和13年1938年に出版されて以来96版を重ね、50万部売れているという。
万葉集と言えば、受験勉強で
春過ぎて夏来るらし白妙の衣干したり天の香具山 持統天皇
ひむがしの野にかげろひの立つ見えて
かへり見すれば月かたぶきぬ 柿本人麿
などを覚えた。この第1句を鎌倉時代に「...夏来にけらし...衣干すてふ...」と藤原定家あたりが勝手に編集して新古今和歌集に採録した、けしからんという論調の一文を国語で学んだ。しかし本書によれば要は万葉仮名の表意部分の読み方次第の許容範囲だということだ。
短歌だけをまず読んで意味を推察してみる。次に解説を読むと、当たっていたり見当違いだったりする。合格率はわずか4-5割だ。千数百年前とはいえ、同じ日本語なのに不思議なことだ。幾つかをご紹介しよう。
巻1:あかねさす紫野行き標野(しめぬ)行き
野守は見ずや君が袖振る 額田王
「あかねさす」は枕詞、標野は御料地、と解説されれば意味は取れる。しかし背景を聞くと歌が生きてくる。額田王は皇太子の子を設けた後、天智天皇に召されていた時に、皇太子に贈った歌だそうだ。染料の紫草の野の御料地をあなたが歩かれ、私に袖を振られるのを御料地の番人に見られはしないでしょうか、という半ば嬉しく半ば心配な女心だ。
巻1:ますらをの鞆(とも)の音すなり
もののふの大臣(おおまへつぎ)楯立つらしも 元明天皇
鞆は弓を射た時に弦を止める革製品。兵士達が鞆を鳴らしている、将軍が軍事訓練をしているようだ、という女帝の不安の表現だとのこと。女帝とはいえ天皇が軍の動きを掌握していなかったらしい所が面白い。
巻2:吾はもはや安見児(やすみこ)得たり
皆人の得がてにすとふ安見児得たり 藤原鎌足
誰もが娶るのは難しいと言っていた美しい安見児を自分は娶った、という喜びの表現だ。古代人の素直な表現が面白い。
巻3:あまざかるひなの長路ゆ恋ひ来れば
明石の門(と)よりやまとしま見ゆ 柿本人麿
遠い田舎から家を恋うる長旅をして、明石海峡から大和が見えた、と石見の国守だった人麿の率直な喜びを表しているが、単純過ぎるなあ。
巻6:ふりさけて みかづき見れば
一目見し人の眉引きおもほゆるかも 大伴家持
三日月を仰ぎ見れば、一目見た美人の眉引きのようだ、という意味だ。
巻14:筑波嶺に雪かも降らる否をかも
愛(かな)しき児ろが布乾さるかも 東歌
白く見えるのは筑波山に雪が降ったのか、否可愛い娘が布を干しているのだろう、という常陸の国に伝わっていた作者不明の歌だ。
万葉短歌は、現代短歌や俳句の先祖で同類と愚かにも思っていたが、全然発想が違うことを発見した。どうしてこれを国語の時間に教えてくれなかったのかなあ。現代短歌や俳句は、百文字二百文字の明示的表現を31文字・17文字に詰め込み、そこから生まれる暗示的世界の広がりを競う所がある。だから詩歌に状況説明を付けることは邪道とされている。一方万葉短歌は、「愛している」と数文字で済む所を比喩を用い尾ひれをつけて美しい31文字に仕上げる「言葉遊び」なのだ。なぜ枕詞のような情報量ゼロで文字数だけ増えるものが存在するのか昔から不思議だったが、やっと分かった。状況説明がないと意味をなさない短歌が多いのも、言葉遊びと考えれば合点がいく。万葉人はTPOに応じて美しい大和言葉を駆使することを存分に楽しんでいたのだ。古希にしてやっとこれを悟った。 以上