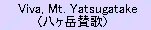 |
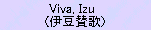 |
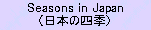 |
|
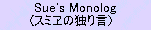 |
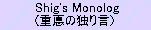 |
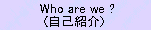 |
|
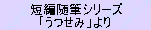 |
 |
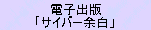 |
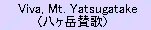 |
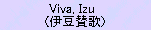 |
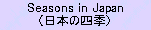 |
|
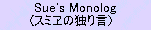 |
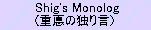 |
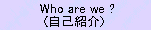 |
|
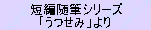 |
 |
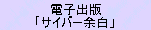 |
益子焼
栃木県の東端、茨城県との県境に近い陶器の町、益子町で冬の日曜日を過ごした。ワイフが宇都宮在住の姉を用事で訪れたついでに、翌日3人で小1時間ドライブして益子まで行った。雪が東京から前橋までは来たが宇都宮地方は雨だったので予定決行とした。私にとっては初めての、義姉・ワイフにとっては十何年ぶりの益子で、「陶器メッセ・益子」という陶器美術館で2時間、昼食で1時間、町の陶器店を巡って3時間を過ごした。
元来の益子の陶器は、一昔前の関東地方・東北地方の家庭にはどこにでもあった日用陶器である。肉厚の甕や食器に光沢のある茶色の釉(うわぐすり)がかかり、上部に加えた黒い釉が下方に不規則に垂れ下がったのが模様となっている。この鉄呈色の茶色を地元では柿釉(かきゆう)と呼ぶ。歴史は意外に新しく、江戸時代後期にこの益子で陶土が発見され、地元の土を砕いて上記のような釉にして、江戸・東京に日用品として大量に売れたことで産業が確立した。後に東京の生活水準が上がって益子焼の売れ行きが頭打ちになると、関東・東北地方に広く販売した。
大正末から昭和初期にかけてこの日用品が美術品に変身する。濱田庄司氏(1894-1978)という英国帰りの若き陶芸家が1924年に益子に移住し、地元と協力しながら陶器の改革を進めた。氏は川崎市溝口の出身で東京高等工業(東工大)を卒業して京都陶磁器試験場に勤め、知り合った英人に招かれて英国で陶芸を学んだ。1968年の文化勲章受章者だ。氏は自ら「京都で道をみつけ、英国で始まり、沖縄で学び、益子で育った」と書いているように陶芸を広く学んだ人で、益子の伝統を活かしつつ世界と日本各地の陶芸技法を取り入れていった。「益子焼」という呼び名も、東京の三越百貨店が展示即売会を催した際に氏が初めて用いたと言われる。
今益子には380の窯元と50の店舗があって、多種多様な陶芸を世に問うている。伝統の益子焼や、その面影を留める陶芸もあり、伝統とはかけ離れた似ても似つかぬ陶芸もある。萩焼そっくりの釉も、有田焼同様の色使いもある。織部もあれば荒々しい備前焼風のものもある。益子の陶土の性質から来る肉厚で重く壊れやすい欠点を新しい陶土で克服し、肉薄で軽い陶芸も増えた。実は美濃焼で開発された陶土を使っているそうだ。最近の記事によれば、地元でも肉薄用の陶土が数年前に開発されたが、消費量の大きい美濃の陶土とはコストで太刀打ちできず、益子の窯元に使って貰えないそうだ。こうなると益子焼とは一体何なのだということになる。意図したかどうかは怪しいが結果論的にはマーケティング戦略の勝利であろう。今や益子は陶器の町として日本中に知られており、外人にも知名度がある。380の窯元が競い合って、益子の伝統を守るというよりは市場性のある多種多様な陶器を開発し適者生存の厳しい闘いを続けているから、消費者の好みに合う陶器が買える。それが益子というブランドを高める。春秋二回の陶器市は、年々観光客が増えているという。
益子の陶器店を結局十数店回ったが、大きく分けて2種類の店があった。一種類は複数の窯元から仕入れ競わせて展示している大きな店だ。典型的には「窯元共販センター」で、大手窯元20社が共同出資した販売会社が出資者の製品を展示し、観光バスで来る忙しい観光客の便を図っている。同種の店で私は半時間もあれこれ見比べて一番気に入った湯飲みを半ダース買った。作りは伝統の益子焼だが、恐らくは藁灰を使ったと思われた白灰色の釉に蓼の花の絵が美しいと褒めたら「陶器は夫が焼き、絵は私が描きました」と近くに居た中年女性が言った。自作陶器の販売支援に来ていたらしい。もう一種類は窯元の直売所で、店ごとに全く異なる作風が見られるから面白い。その一つ大誠窯は、店の裏手に登窯を持ち、薄暗い作業所では2-3人がロクロを回していた。この窯元では、益子焼の伝統を頑なに守る範囲内で近代的なデザインを求めている。栃木県出身のワイフは幼時の記憶を呼び起こす作品が気に入って2-3点購入した。別の店では、昼食時に頼んだ紅茶が陶器のポットで出てきたのが新鮮な驚きだったので、洋風急須を3つ購入した。
陶器長者になったぞ。 以上