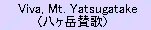 |
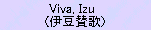 |
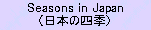 |
|
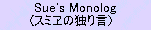 |
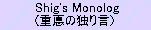 |
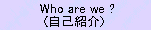 |
|
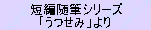 |
 |
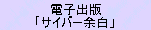 |
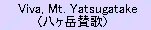 |
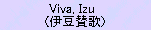 |
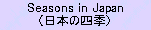 |
|
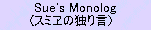 |
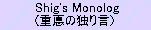 |
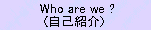 |
|
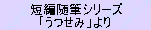 |
 |
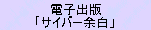 |
実に面白い文庫本に出会った。「新潮文庫ふ12-3 数学者の休憩時間 藤原正彦」 著者は小説家夫妻新田次郎氏・藤原てい氏の次男で昭和18年生まれ、東大数学科修士でお茶大教授、日本エッセイスト・クラブ賞を受けている。著者は数学者だが、本の中で「歌人である伊藤左千夫の文章は、決して流暢でない。武骨でありぶっきらぼうでもある」という。
5月に大学の教養学部の同級会があり、二十数人中冶金屋が2人、化学屋が2人、機械屋と電気屋(私)各1人の6人が集まった。N氏の落語を一席聞いたあとI氏が憂国の辞をほとばしらせて文庫本を数冊皆に配った。冷酒漬けの脳味噌には憂国との関係がよく分からなかったが、私に配られた1冊は有難く持ち帰ったのが上記である。私の1年先輩の著名な物理学者が電子メイル上で短編随筆を(「うつせみ」同様)流しておられ、最近それらを出版されて、それも大変面白いのだが、今回は上記について。
本は数学に関係ない日常生活の随筆から始まる。出産にオロオロしながら立ち会った経験談から、その子の附属小学校入試の親子面接で「幼稚園で喧嘩に巻き込まれた時」と問われ「喧嘩だけは絶対に勝つように指導しております」と流暢に答えて不合格になった話など数編がある。
著者の数学観が表われている次の章が私には特に面白かった。「学ぶ」ことは「生きる」ことに近く、死によってのみ砕かれる業だという。しかし他の学問と違って数学は旧学説が否定されることがないから増殖の一途をたどり、それを習得してから新領域の開拓に取り掛かる数学者の年齢が年々上昇し、その故にあと百年もすると数学の発展は止まり、物理やその他の学問の発達にも致命的なブレーキになるのではないかという。筆者が20代の頃アルティン予想という定理予想を証明しようと6ヶ月苦吟し体力の限界で諦めた。ところが英新鋭数学者が1983年に証明してしまったと聞いて面白くない自分を発見し、功名心のような人間の俗なる心によって美しい真理が掘り起こされる事実に気付かされたという。
数学を将来使いもしない生徒にも高校で教える理由の一つは論理的思考の鍛錬とされているが、筆者はこれは怪しいという。数学者が強い論理は、AだからB、BだからC....と鎖の長い論理で、しかもAなら必ずBになる確定性100%の論理だそうだ。日常生活の論理はAならBとしても、必ずBになるとは限らないのに、数学者はえてして確定性100%であるかの如く「風が吹けば桶屋が儲かる」と独断的に信じたり、不確定性の故に論理的思考がうまく出来なかったりするそうだ。日常の論理で必要なのは、多数あり得る正当な論理の中から適切な論理を選び出す「情緒」だと筆者はいう。筆者は「情緒」に喜怒哀楽だけでなく友情、勇気、愛国心、正義感、美感、思いやりなども含む。この情緒が大学入試から欠落し、従って高校以下の教育から零れ落ちたことが諸悪の根源としている。I氏の憂国との関係が分かった!! また日本人としての高い情緒を持つことが国際化時代に必要で、外人・外国の真似をすることが国際化ではないと戒めている。
数学が論理的思考の役に立たぬ以上、非数学的分野に進む人が数学教科で学ぶべきものは(1)数学的感覚・センスと(2)考える喜びと(3)数学美への感受性だとし、そのためには幾何学がベストの教材だから、利用範囲が狭くても教科に復活すべしと主張している。
本の最後の1/3は「サウダーデの石」という短編ノンフィクションだった。英人小泉八雲と同様に、ポルトガルから来日して故国に日本を紹介し続けた文学者モラエスを、「孤愁−サウダーデ」という新聞連載小説に書いている最中の1980年に筆者の父新田次郎氏は他界した。その前年、モラエスの取材で父が訪れたポルトガルの田舎を1981年に筆者が訪れた。父の取材ノートを片手に父の旅をなぞった旅行記だった。サウダーデとは、今は近くにない愛するものを懐かしむ甘美な感情を表すポルトガル語特有の単語だそうで、モラエスが故国を偲んだ孤独なサウダーデを父が書こうとし、その父へのサウダーデでその足跡をたどったと筆者はいう。両親譲りなのであろう魅力的な文体を追ううちに、筆者自身が類希な情緒の人であることに気付いた。職業を間違えたんじゃないかな。 以上