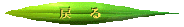 水野家(てるちゃん)のホームページTOPへ
水野家(てるちゃん)のホームページTOPへ

| 番号 | 万葉名 | 和名 | 科名 | 読み人 | 万葉集の歌 | 巻 |
|
(例) 075 |
すみれ | すみれ | すみれ | 山部宿禰赤人の歌 |
春の野にすみれ採みにと来し吾ぞ 野をなつかしみ一夜宿にける |
巻8-1424 |
| 001 | あおいぐさ | ふとい | かやつりぐさ | * |
上つ毛野伊奈良の沼の大藺草 よそに見しよは今こそ勝れ |
巻14-3417 |
| 002 | あかね | あかね | あかね | * |
茜さす紫野行き標野行き 野守は見ずや君が袖振る |
巻1-20 |
| 003 | あさがお | ききょう | ききょう | * |
朝貎は朝露負ひて咲くといへど 夕陰にこそ咲きまさりけれ |
巻10-2104 |
| 004 | あし | あし | かほん | * |
葦辺ゆく鴨の羽交に霜零りて 寒き夕は大和し念ほゆ |
巻1-64 |
| 005 | あじさい | あじさい | ゆきのした | * |
紫陽花の八重咲く如く やつ世にを いませわが夫子見つつしのばむ |
巻20-4448 |
| 006 | あしび | あしび | つつじ |
甘南備の 伊香の眞人 |
磯かげの見ゆる池水照るまでに 咲ける馬酔木の散らまく惜しも |
巻20-4513 |
| 007 | あずさ |
みずめ、 よぐそみねはり |
かばのき | * |
梓弓引きて弛べぬ丈夫や 恋とふものを忍びかねてむ |
巻12-2987 |
| 008 | あは | あわ | かほん | * |
ちはやぶる神の社し無かりせば 春日の野辺に栗蒔かましを |
巻3-404 |
| 009 | あふち | せんだん | せんだん | * |
珠に貫く棟を宅に植ゑたらば 山霍公鳥離れず来むかも |
巻17-3910 |
| 010 | あふひ |
ふゆあおい、 かんあおい |
あおい | * |
梨棗黍に栗嗣ぎ延ふ田葛の 後も逢はむと葵花咲く |
巻16-3834 |
| 011 | あべたちばな | こうじみかん | さんしょう | * |
吾妹子に逢はず久しもうまし物 阿部橘の蘿生すまでに |
巻11-2750 |
| 012 | あやめぐさ | しょうぶ | さといも |
大友家持の 霍公鳥の歌 |
霍公鳥待てど来喧かず菖蒲草 玉に貫く日をいまだ遠みか |
巻8-1490 |
| 013 | あをな | かぶら | かぶらな | * |
食薦敷き蔓菁煮待ち来梁に 行騰かけて息むこの公 |
巻16-3825 |
| 014 | いちし | ひがんばな | ゆり | * |
路の辺の壱師の花のいちしろく 人皆知りぬわが恋妻は |
巻11-2480 |
| 015 | いちひ | いちいがし | ぶな |
乞食者の歌 −長歌 |
前略…あしひきのこの片山に二つ立つ 櫟本に梓弓八つ手挟み …後略 |
巻16-3885 |
| 016 | いね | いね | かほん | * |
恋ひつつも稲葉かき別け家居れば 乏しくもあらず秋の夕風 |
巻10-2230 |
| 017 | いはいづら | すべりひゆ | すべりひゆ | 武蔵の国の歌 |
入間道の大家が原のいはゐづら 引かばぬるぬる吾にな絶えそね |
巻14-3378 |
| 018 | いはづな | ていかかづら | きょうちくとう | * |
石綱のまたをちかへりあをによし 奈良の京師をまたも見むかも |
巻6-1046 |
| 019 | うきまなご | うきくさ | うきくさ | * |
解衣の恋ひ乱れつつ浮沙 生きても吾はあり渡かも |
巻11-2504 |
| 020 | うけら | おけら | きく | 武蔵の国の歌 |
恋しけば袖も振らむを武蔵野の うけらか花の色に出なゆめ |
巻14-3376 |
| 021 | うのはな |
うつぎ、 うのはな |
ゆきのした | * |
五月山卯の花月夜霍公鳥 聞けども飽かずまた鳴かぬかも |
巻10-1953 |
| 022 | うはぎ | よめな | きく | * |
春日野に煙立つ見ゆをとめ等し 春野の菟芽子採みて煮らしも |
巻10-1879 |
| 023 | うまら |
のばら、 のいばら |
ばら | 天羽の上丁丈部の鳥 |
道の辺の荊の未にはほ豆の からまる君を離れか行かむ |
巻20-4356 |
| 024 | うめ | うめ | ばら | * |
春さればまづ咲く宿の梅の花 ひとり見つつや春日暮さむ |
巻5-818 |
| 025 | うも | さといも | さといも |
長忌寸意吉麻呂の 荷葉を詠める歌 |
蓮葉はかくこそあるもの意吉麻呂が 家なるものは芋の葉にあらし |
巻16-3826 |
| 026 | え | えのき | にれ | * |
わが門の榎の実もり喫む百千鳥 千鳥は来れど来ぞ来まさぬ |
巻16-3872 |
| 027 | えぐ | くろぐわい | かやつりぐさ | * |
君がため山田のの沢に恵具採むと 雪消の水に裳の裾ぬれぬ |
巻10-1839 |
| 028 | おぎ | おぎ | かほん | * |
葦辺なる荻の葉さやぎ秋風の 吹き来るなべに雁鳴き渡る |
巻10-2134 |
| 029 | おみなへし | おみなえし | おみなえし | * |
手に取れば袖さへにほふ女郎花 この白露に散らまく惜しも |
巻10-2115 |
| 030 | おみのき | もみ | まつ | * |
前略…み湯の上の樹群を見れば おみの木も生い継ぎにけり …後略 |
巻3-322 |
| 031 | おもいぐさ | なんばんぎせる | はまうつぼ | * |
道の辺の尾花が下の思草 今さらになぞ物か念はむ |
巻10-2270 |
| 032 | かえるで | かえで | かえで | * |
わが屋戸に黄変つ鶏冠木見るごとに 妹を懸けつつ恋ひぬ日はなし |
巻8-1623 |
| 033 | かおばな | ひるがお | ひるがお | * |
高円の野辺の容花おもかげに 見えつつ妹は忘れかねつも |
巻8-1630 |
| 034 | かきつばた | かきつばた | あやめ |
大友宿禰家持の 作れる |
かきつばた衣に摺りつけ丈夫 のきそい猟する月は来にけり |
巻17-3921 |
| 035 | かし |
かし、 あらかし |
ぶな |
河内の大橋を 独去く娘子を見る歌 −長歌 |
前略…若草の夫かあるらむ 橿の実の独か宿らむ …後略 |
巻9-1742 |
| 036 | かしわ | かしわ | ぶな | * |
稲見野のあから柏は時あれど 君を吾が思ふ時は実なし |
巻20-4301 |
| 037 | かずのき | ぬるで | うるし | * |
足柄のわを可鶏山のかづの木の 我をかづさねもかづさかずとも |
巻14-3432−東歌 |
| 038 | かたかご | かたくり | ゆり | * |
もののふの八十をとめらがくみまがふ 寺井の上の堅香子の花 |
巻19-4143 |
| 039 | かつら | かつら | かつら | * |
向つ岳の若楓の木下枝取り 花待つい間に嘆きつるかも |
巻7-1359 |
| 040 | かには | ちょうじざくら | ばら |
山部宿禰赤人の 作れる歌 |
前略…敷細の枕も纒かず桜皮纒き 作れる舟に眞楫貫き …後略 |
巻6-942 |
| 041 | かへ | かや | いちい |
大友家持の歌 −長歌 |
前略…直向ひ見む時までは松柏の 栄えいまさね尊き吾が君 |
巻19-4169 |
| 042 | かや | すすき | かほん | * |
わが夫子は仮廬作らす草なくば 小松が下の草を刈らさね |
巻1-11 |
| 043 | からあい | けいとう | ひゆ | * |
秋さらば影にもせむとわが蒔きし 韓藍の花を誰が採みけむ |
巻7-1362 |
| 044 | からたち | からたち | みかん | * |
枳の棘原刈り除け倉立てむ 屎遠くまれ櫛造る刀自 |
巻16-3832 |
| 045 | かわやぎ | ねこやなぎ | やなぎ | * |
河暇鳴く六田の河の川楊の ねもころ見れど飽かぬ河かも |
巻9-1723 |
| 046 | きみ | きび | かほん | * |
古りにし人の食せる吉備の酒 病めばすべなし貫簀賜らむ |
巻4-554 |
| 047 | きり | あおぎり | あおぎり | * |
大伴の淡等謹みて状す 梧桐の日本琴一面 |
巻5-810の題詞 |
| 048 | くくみら | にら | ゆり | * |
伎波都久の岡の莖韮われ摘めど 篭にも満た無ふ夫なと摘まさね |
巻14-3444 |
| 049 | くず | くず | まめ | * |
雁がねの寒く鳴きしゆ水莖の 岡の葛葉は色づきにけり |
巻10-2208 |
| 050 | くそかづら |
へくそかづら、 かばねつぐさ |
あかね | * |
崑莢に延ひおほどれる屎葛 絶ゆることなく宮仕せむ |
巻16-3855 |
| 051 | くり | くり | ぶな | * |
三栗の那賀に向へる曝井の 絶えず通はむ彼所に妻もが |
巻9-1745 |
| 052 | くれない | べにばな | きく | * |
紅に衣染めまく欲しけれども 著くにほはばや人の知るべき |
巻7-1297 |
| 053 | くわ | やまぐわ | くわ | * |
たらちねの母のその業の桑すらに 願へば衣に着るとふものを |
巻7-1357 |
| 054 | こけ | こけ | すぎごけ、せにごけ | * |
み芳野の青根が峰の蘿むしろ 誰か織りけむ経緯無しに |
巻7-1120 |
| 055 | こなら | こなら | ぶな | * |
下毛野みかもの山の小楢のす まぐはし児らは誰が筍か持たむ |
巻14-3424 |
| 056 | このてがしわ | このてかしわ | ひのき | * |
千葉の野の児手柏の含まれど あやにかなしみ置きてたち来ぬ |
巻20-4387 |
| 057 | こも | まこも | かほん | * |
飼飯の海の庭よくあらし刈薦の 乱れ出づ見ゆ海人の釣舟 |
巻3-256 |
| 058 | さいかち |
さいかち、 かわらふじ |
まめ | * |
菎莢に延ひおどれる屎葛 絶ゆることなく宮仕せむ |
巻16-3855 |
| 059 | さかき |
さかき、 まさかき |
つばき | * |
前略…奥山の賢木の枝に 白香著け木綿とりつけて…後略 |
巻3-379 |
| 060 | さきくさ | みつまた | じんちょうげ | * |
春さればまづ三枝の幸くあらば 後にも逢はむ莫恋ひそ吾妹 |
巻10-1895 |
| 061 | さくら | やまざくら | ばら | * |
春雨のしくしく降るに高円の 山の桜はいかにあるらむ |
巻8-1440 |
| 062 | ささ | くまざさ | かほん | * |
小竹の葉はみ山もさやに乱げども 吾は妹思う別れ来ぬれば |
巻2-133 |
| 063 | さなかづら |
さねかづら、 びなんかづら |
もくれん | * |
さね葛のちも逢はむと夢のみに 誓約ひぞわたる年は経につつ |
巻11-2479 |
| 064 | さはあららぎ | さわひよどり | きく | * |
天皇、大后、共に大納言藤原家に幸し日、 黄葉せる沢蘭一株を抜き取りて …後略 |
巻19-4268の題詞 |
| 065 | しい | しい | ぶな | 有間の皇子の歌 |
家にあれば筍に盛る飯を草枕 旅にしあれば椎の葉に盛る |
巻2-142 |
| 066 | しきみ | しきみ | もくれん | * |
奥山のしきみが花の名の如や しくしく君に恋ひわたりなむ |
巻20-4476 |
| 067 | しだくさ | のきしのぶ | うらぼし | * |
わが屋戸の軒の子太草生ふけれども 恋忘れ草見れどいまだ生ひず |
巻11-2475 |
| 068 | しぬ |
しのだけ、 しの |
かほん | * |
うち靡く春さり来れば小竹の末に 尾羽うち触りて鶯鳴くも |
巻10-1830 |
| 069 | しば | しば | かほん | * |
立ち易り古き都となりぬれば 道の芝草長く生ひにけり |
巻6-1048 |
| 070 | しらかし | しらかし | ぶな | * |
あしひきの山道も知らず白橿の 枝もとををに雪の降れれば |
巻10-2315 |
| 071 | しりくさ | さんかくい | かやつりぐさ | * |
湖葦に交れる草の知草の 人みな知りぬ吾が下思 |
巻11-2468 |
| 072 | すが、すげ | すげ | かやつりぐさ |
大納言 大伴の卿の歌 |
奥山の菅の葉しのぎふる雪の 消なば惜しけむ雨なふりそね |
巻3-299 |
| 073 | すぎ | すぎ | すぎ | * |
わが夫子を大倭へ遺りてまつしたす 足柄山の杉の木の間か |
巻14-3363 |
| 074 | すず | やのたけ | かほん | 久米の禅師の歌 |
み薦刈る信濃の真弓わが引けば うま人さびて否とと言はむかも |
巻2-96 |
| 075 | すみれ | すみれ | すみれ | 山部宿禰赤人の歌 |
春の野にすみれ採みにと来し吾ぞ 野をなつかしみ一夜宿にける |
巻8-1424 |
| 076 | すもも | すもも | ばら | 大伴家持の歌 |
わが園の李の花か庭に落りしは はだれのいまだ残りたるかも |
巻19-4140 |
| 077 | せり | せり | せり | 薩の妙観の歌 |
丈夫と思へるものを刀佩きて かにはの田井に芹子ぞ採みける |
巻20-4456 |
| 078 | たく | こうぞ | くわ | * |
梯衾新羅へいます君が目を 今日か明日かと斉ひて待たむ |
巻15-3587 |
| 079 | たけ | まだけ | かほん |
大伴家持の 作れる歌 |
わが屋戸のいささ群竹吹く風の 音のかそけきこの夕かも |
巻19-4291 |
| 080 | たちばな |
みかん、 たちばな |
みかん | * |
橘の蔭ふむ路の八衢に ものをぞ念ふ妹に逢はずて |
巻2-125 |
| 081 | たで |
たで、 やなぎたで |
たで | * |
わが屋戸の穂蓼古幹採み生し 実になるまでに君をし待たむ |
巻11-2759 |
| 082 | たまかづら | ごとうづる | ゆきのした | * |
玉葛花のみ咲きて成らざるは 誰が恋ならめわが恋ひ念ふを |
巻2-102 |
| 083 | たまばはき | こうやぼうき | きく |
大友家持の 作れる歌 |
始春の初子の今日の玉箒 手に執るからにゆらく玉の緒 |
巻20-4493 |
| 084 | たわみずら | ひるむしろ | ひるむしろ | * |
安波をろのをろ田に生はるたはみ曼 引かばぬるぬる吾を言な絶え |
巻14-3501 |
| 085 | ちさ | えごのき | えごのき |
大伴宿禰家持の 輿に依りて作れる歌 −長歌 |
前略…世の人の立つる言立ちさの花 咲ける盛に…後略 |
巻18-4106 |
| 086 | ちち | いぬびわ | * | 長歌 |
ちちの実の父の命柞葉の母の命 おぼろかに情尽して念ふらむ …後略 |
巻19-4164 |
| 087 | ちばな |
つばな、 ちがや |
かほん | * |
戯奴がためわが手もすまに春の野に 抜ける茅花ぞ食して肥えませ |
巻8-1460 |
| 088 | つがのき | つが | まつ |
柿本の朝臣人麻呂の 作れる歌 −長歌 |
前略…橿原の 日知の御代ゆ 生れましし 神のことごと つがの木の いやつぎつぎに …後略 |
巻1-29 |
| 089 | つき | けやき | にれ | * |
天飛ぶや 軽の社の斉槻 幾世まで あらむ隠嬬ぞも |
巻11-2656 |
| 090 | つきくさ | つゆくさ | つゆくさ | * |
鴨頭草に衣ぞ染むる君がため 綵色ごろも摺らむと念ひて |
巻7-1255 |
| 091 | つきぬちのかつら |
もくせい、 ぎんもくせい |
もくせい | * |
黄葉する時になるらし月人の かつらの枝の色づく見れば |
巻10-2202 |
| 092 | つぎね | ひとりしづか | ちゃらん | 長歌 |
つぎねふ山城道を他夫の 馬より行くに…後略 |
巻13-3314 |
| 093 | つげ |
つげ、 ほんつげ |
つげ |
興に依りて 大友の宿禰家持の 作れり |
嬢子らが後のしるしと黄楊小櫛 生ひ更り生ひて扉きけらしも |
巻19-4212 |
| 094 | つちはり |
めはじき、 えんれいそう |
ゆり | * |
わが屋前に生ふる土針心ゆも 想はぬ人の衣に摺らゆな |
巻7-1338 |
| 095 | つつじ | やまつつじ | つつじ | * |
山越えて遠津の浜の石つつじ わが来るまでに含みてあり待て |
巻7-1188 |
| 096 | つづら | あおつづらふじ | あおつづらふじ | * |
上つ毛野安蘇山つづら野を広み 延ひにしものを何か絶えせむ |
巻14-3434 |
| 097 | つばき |
やぶつばき、 やまつばき |
つばき |
大伴の宿禰家持の 館に宴せる歌 |
奥山の八峰の椿つばらかに 今日は暮らさね丈夫のとも |
巻19-4152 |
| 098 | つぼすみれ | つぼすみれ | すみれ | 高田の女王の歌 |
山振の咲きたる野辺の都保須美礼 この春の雨に盛なりけり |
巻8-1444 |
| 099 | つまま | たらのき | くす | 大伴の宿禰家持の歌 |
磯の上の都万麻を見れば根を延へて 年深からし神きびにけり |
巻19-4159 |
| 100 | つみ | やまぐわ | くわ | 若宮の年魚麻呂の歌 |
古に梁打つ人の無かりせば 此間もあらまし柘の枝はも |
巻3-387 |
| 101 | ときじきふじ | なつふじ | まめ | 大伴の宿禰家持の歌 |
わが屋前の時じき藤のめずらしく 今も見てしか妹咲容を |
巻8-1627 |
| 102 | ところづら | ところ | やまいも | * |
皇祖神の神の宮人冬薯蕷葛 いや常しくに吾かへり見む |
巻7-1133 |
| 103 | なぎ | こなぎ | みずあおい | * |
上つ毛野伊香保の沼に殖子水葱 かく恋ひむとや種求めけむ |
巻14-3415 |
| 104 | なし | やまなし | ばら | * |
露霜のさむき夕の秋風に 黄葉にけりも妻梨の木は |
巻10-2189 |
| 105 | なつめ | なつめ | くろうめどき | * |
玉掃刈り来鎌麻呂室の樹と 棗が本をかき掃かむため |
巻16-3830 |
| 106 | なでしこ | かわらなでしこ | なでしこ | * |
野辺見れば瞿麦の花咲きにけり わが待つ秋は近づくらしも |
巻10-1972 |
| 107 | なよたけ | めだけ | かほん |
柿本の朝臣人の 作れる歌 −長歌 |
秋山のしたふる妹なよ竹の とをよる子らはいかさまに 念い居れか…後略 |
巻2-217 |
| 108 | なら |
なら、 こなら |
ぶな | * |
御猟する雁羽の小野の櫟柴の 馴れは益らず恋こそまれまされ |
巻12-3048 |
| 109 | にこぐさ | はこねしだ | うらぼし | * |
蘆垣の中の似児草にこよかに 我と咲まして人に知らゆな |
巻11-2762 |
| 110 | ぬなは | じゅんさい | はす | * |
わが情ゆたにたゆたに浮蓮 辺にも沖にも寄りかつましじ |
巻7-1352 |
| 111 | ぬばたま | ひおうぎの種子 | あやめ | * |
居明かして君をば待たむぬばたまの わが黒髪に霜は降るとも |
巻2-89 |
| 112 | ねつこぐさ | おきなぐさ | きんぽうげ | * |
芝付の美宇良崎なる根都古草 相見ずあらば我恋ひめやも |
巻14-3508 |
| 113 | ねぶ |
ねむのき、 ねぶた |
まめ | * |
昼は咲き夜は恋ひ宿る合歓木の花 君のみ見めや戯奴さへに見よ |
巻8-1461 |
| 114 | はぎ | はぎ | まめ | 大伴の宿禰家持の歌 |
丈夫の呼び立てしかばさを鹿の 胸分け行かむ秋野芽子原 |
巻20-4320 |
| 115 | はじ | はぜのき | うるし |
大伴家持の歌 −長歌 |
前略…高千穂の岳に天降りし皇祖の 神の御代より梔弓を手握り持たし |
巻20-4465 |
| 116 | はちす | はす | はす | * |
ひさかたの雨も降らぬか蓮葉に 渟れる水の玉に似たらむ見む |
巻16-3837 |
| 117 | はながつみ |
まこも (出穂せるもの) |
かほん |
中臣の女郎の、 大伴の宿禰家持に 贈れる歌 |
おみなえし佐紀沢に生ふる花勝美 かつても知らぬ恋もするかも |
巻4-675 |
| 118 | はなたちばな | たちばな | みかん | * |
わが屋前の花橘の何時しかも 珠に貫くべくその実なりなむ |
巻8-1478 |
| 119 | はねず | にわざくら | ばら | * |
夏まけて咲きたるはねずひさかたの 雨うち零らばうつろひなむか |
巻8-1485 |
| 120 | ははそ | こなら | ぶな | * |
山科の石田の小野の柞原 見つつや公が山道越ゆらむ |
巻9-1730 |
| 121 | はまゆふ | はまおもと | ひがんばな | * |
み熊野の浦の浜木綿百重なす 心は念へど直に逢わぬかも |
巻4-496 |
| 122 | はり | はんのき | かばのき | * |
引馬野ににほふ榛原入り乱れ 衣にほはせ旅のしるしに |
巻1-57 |
| 123 | ひえ | のびえ | かほん | * |
打ちし田に稗は数多にありといへど 択えし我ぞ夜ひとり宿る |
巻11-2476 |
| 124 | ひかげかづら | ひかげのかづら | ひかげのかづら | * |
あしひきの山下日蔭蘰ける 上にや更に梅を賞ばむ |
巻179-4278 |
| 125 | ひさぎ | あかめかしわ | たかとうだい |
山部の宿禰赤人の 作れる歌 |
ぬばたまの夜の深けぬれば久木生ふる 清き河原に千鳥数鳴く |
巻6-925 |
| 126 | ひし | ひし | あかばな | * |
君がため浮沼の池の菱採むと 我が染めし袖濡れにけるかも |
巻7-1249 |
| 127 | ひめゆり | ひめゆり | ゆり | * |
夏の野の繁みに咲ける姫百合の 知らえぬ恋は苦しきものぞ |
巻8-1500 |
| 128 | ひる | のびる | ゆり | * |
ひしほすに蒜搗き合へて鯛願ふ 吾にな見せそ水葱の羹 |
巻16-3829 |
| 129 | ふじ | ふじ | まめ | * |
藤浪の花は盛になりにけり 平城の京を思ほすや君 |
巻3-330 |
| 130 | ふぢばかま | ふじばかま | きく | * |
芽子の花尾花葛花瞿麦の花 女郎花また藤袴朝貌の花 |
巻8-1538 |
| 131 | ほほがしわ | ほほのき | もくれん | * |
わが兄子が捧げて持てる厚朴 あたかも似るか青ききぬがさ |
巻19-4204 |
| 132 | ほよ | やどりぎ | やどりぎ | 大伴家持の歌 |
あしひきの山の木末の寄生取りて 挿頭しつらく千年寿ぐとぞ |
巻18-4136 |
| 133 | まき | ひのき | ひのき | * |
古にありけむ人もわが如か 三輪の檜原に挿頭折りけむ |
巻7-1118 |
| 134 | まき | ひのき | ひのき |
小田の事の、 勢の山の歌 |
真木の葉のしなふ勢の山思ばずて わが越えゆけば木の葉知りけむ |
巻3-291 |
| 135 | まつ |
まつ、 あかまつ、 くろまつ |
まつ | 紀の朝臣鹿人の歌 |
茂岡に神さび立ちて栄えたる 千代松の樹の歳の知らなく |
巻6-990 |
| 136 | まめ |
のまめ、 つるまめ |
まめ |
天羽の郡の 上丁丈部の鳥の歌 |
道の辺の荊の未にはほ豆の からまる君を離れか行かむ |
巻20-4352 |
| 137 | まゆみ | まゆみ | にしきぎ | * |
南淵の細川山に立つ橿弓束 纒くまで人に知らえじ |
巻7-1330 |
| 138 | みくさ |
すゝき、 かや |
かほん | 額田王の歌 |
秋の野のみ草苅り葺き宿れりし 兎道の宮処の仮廬し思ほゆ |
巻1-7 |
| 139 | みつながしわ | かくれみの | うらぼし | 歌の序 |
皇后の 紀伊の国に遊行して熊野の岬に到り、 その処の御綱葉を取りて返りた |
巻2-90 |
| 140 | むぎ | おおむぎ | かほん | * |
馬柵越しに麦喰む駒の詈られゆれど 猶し恋しく思ひかねつも |
巻12-3096 |
| 141 | むぐら | かなむぐら | くわ |
左の大臣 橘の卿の歌 |
葎はふ賤しき屋戸も大皇の 坐さむと知らば玉敷かましを |
巻19-4270 |
| 142 | むらさき | むらさき | むらさき |
笠の女郎の 大伴の宿禰家持に 贈れる歌 |
託馬野に生ふる紫草衣に染め いまだ着ずして色に出にけり |
巻3-395 |
| 143 | むろのき |
むろ、 ねず、 もろ |
ひのき |
太宰の卿 大伴の卿の歌 |
吾妹子が見し鞆の浦のむろの木は 常世にあれど見し人ぞ無き |
巻3-446 |
| 144 | もむにれ |
にれ、 はるにれ |
にれ |
乞食者の詠 −長歌 |
前略…あしひきのこの片山の もむにれを五百枝剥ぎ垂り |
巻16-3886 |
| 145 | もも | もも | ばら | 大伴家持の歌 |
春の苑紅にほふ桃の花下 照る道に出で立つをとめ |
巻19-4139 |
| 146 | ももよぐさ | つゆくさ | つゆくさ | * |
父母が殿の後方のももよぐさ 百代いでませわが来るまで |
巻20-4326 |
| 147 | やなぎ | しだれやなぎ | やなぎ | * |
浅みどり染めかけたりと見るまでに 春のやなぎは芽えにけるかも |
巻10-1847 |
| 148 | やまあい | やまあい | たかとうだい | * |
級照る 片足羽河の さ丹塗の 大橋の上ゆ くれないの 赤裳裾引き 山藍用ち 摺れる衣着て…後略 |
巻9-1742 |
| 149 | やますげ | やぶらん | ゆり | 柿本人麻呂の歌 |
ぬばたまの黒髪山の山草に 小雨零りしきしくしく思ほゆ |
巻11-2456 |
| 157 | やまたず | にわとこ | すいかずら | * |
君が行き日長くなりぬ山多豆の 迎へを行かむ待つには待たじ |
巻2-90 |
| 150 | やまたちばな | やぶこうじ | やぶこうじ | 大伴家持の歌 |
この雪の消遺る時にいざ行かな 山橘の実の光るも見む |
巻19-4226 |
| 151 | やまちさ | えごのき | えごのき | * |
気の緒に念へる吾を山萵苣の 花にか君が移ひぬらむ |
巻7-1360 |
| 152 | やまぶき | やまぶき | ばら | 厚見の王の歌 |
蝦鳴く甘南備河に彰見えて 今や咲くらむ山振の花 |
巻8-1435 |
| 153 | ゆづるは | ゆずりは | たかとうだい | 弓削の皇子の歌 |
古に恋ふるとりかも弓弦葉の 御井の上より鳴きわたり行く |
巻2-111 |
| 154 | よもぎ | よもぎ | きく |
大伴の宿禰家持の 作れる −長歌 |
前略…ほととぎす来鳴く五月の 菖蒲草蓬蘰ぎ酒宴 …後略 |
巻18-4116 |
| 155 | わすれぐさ | のかんぞう | ゆり |
師大伴の卿の歌 (大伴旅人) |
萱草わが紐に付く香具山の 故りにし里を忘れじがため |
巻3-334 |
| 156 | わらび | わらび | うらぼし | * |
石激る垂水の上のさ蕨の 萌え出づる春になりにけるかも |
巻8-1418 |
