SYSTEMA by MITO YUKO
![]() 鉄道のどこが面白いのか?
鉄道のどこが面白いのか? ![]()
by MITO YUKO
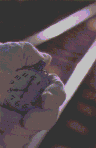
====
鉄道はダイナミックな「生命体」
◇ 鉄道の本を書いたというと、よく出くわす反応は
「わたしはあまり鉄道には関心がないほうですから…」
というものだ。
多くの人は、どうやら鉄道の話というと、
鉄道マニアや鉄道関係者など、何か特殊な思い入れを
持った人々の興味の対象であるかのようにとらえているようだ。
確かに、蒸気機関車の型式や新型車両の性能を空で論じられる人や、
時刻表の細かい数字に見入って無限のロマンに浸っている人の姿を
見ていると、「とても自分にはついてゆけない」という思いもする
ことだろう。
◇ 通常、乗客として鉄道を利用する人が、列車運行の仕組みに強い関心
を抱くことはない。
「早くこの混雑列車から逃れたい」とか「もうちょっと愛想のよい
サービスをしてくれればよいのに…」とか、ときどき思うだけで、
列車運行の仕組みに関心がいくのは、それこそ列車が大幅に遅れて、
散々な目に遭ったときぐらいのものである。
◇ 鉄道はいつも安全で正確で当たり前のもの。
昔からそうだったし、これからもそうだと、
どこかで思っている。
だが、改めて考えてみると、列車をいつも定時に発着させることは
並のことではないはずなのである。
◇ 最近は気象予測技術が発達したので、
明日の天気が晴れであるか雨であるかは、かなりの度合いで
的中する。
だが、1か月後とか1年後の今日が
晴れであるか雨であるかを言い当てるのはむずかしい。
来月の為替相場、半年後の石油価格、来年の景気動向、
もっと身近には目の前の商品の1か月後の売り上げ、
来年の収入だって、なかなか予想通りにはならないものだ。
むしろ思った通りに物事が運ぶときに「してやったり!」と
大喜びするのが人間の楽しみというものでもある。
◇ 通常、人間の生活に不確実性はつきものである。
ところが鉄道空間では、
いつも未来は先取りされているかのようだ。
ひとたび時刻表に記されると、
「何月何日、何時何分発の、どこ行の列車に乗れば、
何時何分、どこどこ駅に着く」と、
日本全国のすべての駅を発着するすべての列車が、
ダイヤが改正されるまでの365日後の未来にわたって、
ほぼ予定通りに発着する。
乗客もそれをあたかも決められた事実であるかのごとく
思って行動する。
◇ 鉄道だけがこの世の不確実性から逃れているわけでも、
未来を先取りする能力があらかじめ天から与えられている
わけでもないのに、
どうして日本の鉄道は、いつも予定通りに正確に運行できる
のだろうか?
乗客も、どうしてそれを当たり前のように考えるのか?
時計のように正確な鉄道をもつにいたった日本社会とは、
一体、何なのか?
◇ 改めて考えてみると、列車運行の仕組みは、
われわれの身近にある大きな謎なのである。
◇ 見ての通り、鉄道は、
車両や線路、トンネルや橋梁、架線やケーブル、
信号装置や駅施設などからなる「ハードウェアの塊」だ。
だが、これほどの重装備産業ともなれば、
それを運営する知恵というものも、大規模で複雑なものになる。
◇ 普段、われわれ乗客の目に触れることは全くないのだが、
鉄道には「ソフトウェアの塊」としての性格もある。
実をいうと、定時運転の謎を探ることは、
列車を走らせる「ソフトウェアの塊」としての鉄道システムを
とらえることでもある。
◇ そして「ソフトウェアの塊」としての鉄道は、
意外なほどに日本社会の発想そのものなのだ。
地を這う線路に制約される鉄道は、
植物のように日本社会に根を張って、
いつも地域社会の発展のリズムと呼応しながら育ってきた。
◇ それだけにこの産業には、日本社会の特徴や課題が
映し出されているし、
鉄道のリズムは日本社会に刷り込まれてもいる。
20世紀の大衆社会のリズムは、鉄道のリズムと呼応しながら
つくられてきたし、
鉄道が求める公共ルールは
知らず知らずのうちに、われわれの社会の常識やルール
にもなってきている。
◇「ソフトウェアの塊」としての鉄道には、
鉄道100年の知恵ばかりでなく、
千年を超える日本社会の知恵さえも
組み込まれているのだ。
◇ 過去100年、日本社会は「急激な変化」の中にあった。
社会が変われば、鉄道の技術が変わる。
鉄道の技術が変われば、社会も変わる…と、
定刻通りに発着する鉄道は、
その時々の鉄道技術と、その時々の社会環境の変化との
微妙なバランスの中で実現してきた。
◇だがついに日本鉄道も、
100年来続けてきた定時運転を、
いま超えようとしている。
鉄道を動かすゲームのルールを根本から変えて、
日本社会に新たなリズムを刻もうとしている。
◇ 鉄道は意外に面白い。
そこにはダイナミックな「生命体」の息吹さえある。
◇ “食わず嫌い”だった方にも読んでいただこうと、
専門用語は極力使わず、わかりやすく表現することを心掛けた。
◇ 細かな機械の話は一切ないのである。
2001.1 三戸祐子
===
鉄道のどこが面白いのか?
風が吹けば桶屋が儲かる WHO'S YUKO ? ご意見はこちら
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() copyright 2001 mito yuko All rights reserved
copyright 2001 mito yuko All rights reserved ![]()